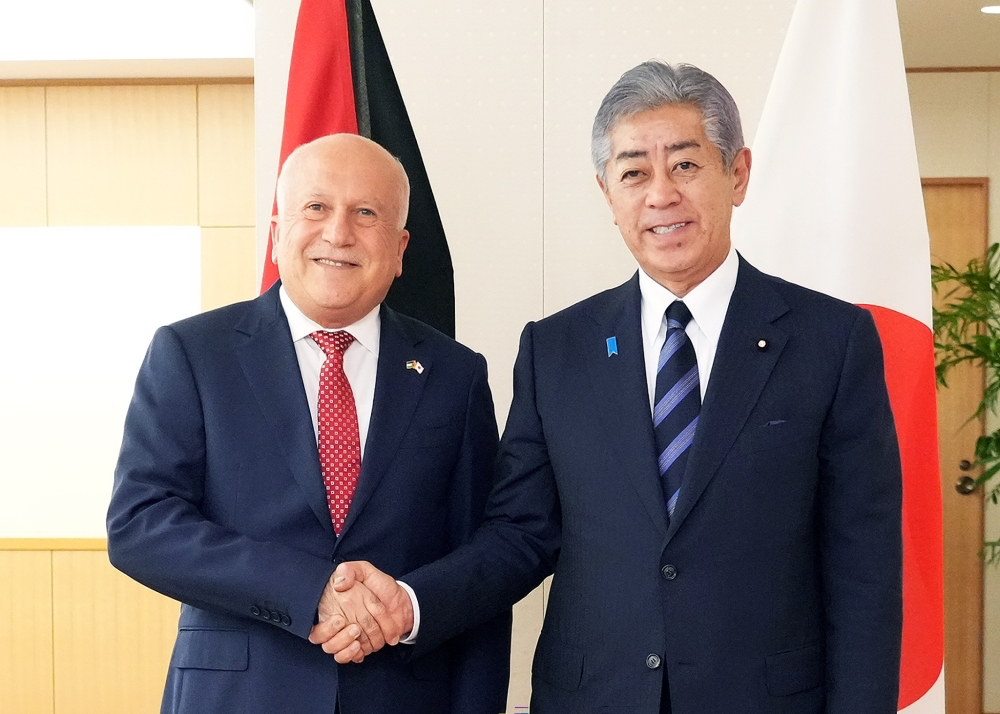- ARAB NEWS
- 01 Aug 2025
不発弾の時限信管が空港での爆発の原因か

東京:2024年10月に宮崎空港で不意に爆発した戦時中の米国製爆弾には、信管の作動を遅らせるよう設計された時限信管が含まれていた可能性が高いことが、防衛省の調査で明らかになった。
専門家は、この爆弾を第二次世界大戦中に米軍が投下した爆弾のひとつであると特定した。この爆弾は化学反応を利用して信管を作動させるもので、日本軍の特攻作戦に使用される基地を一時的に無力化することを目的としていた。
来年の終戦80周年を前に、この爆発は、戦時中の米国による日本への空襲の残した遺産がいまだに残っていることを思い起こさせるものとなった。
10月2日午前8時前、宮崎市の空港で爆発が起こった。地下に埋められていた500ポンドの爆弾が自然発火し、誘導路の近くに長さ約7メートル、幅4メートル、深さ1メートルのクレーターを作った。爆発の直前に、4機の航空機がこの誘導路を使って離陸していた。
その日のうちに、佐賀県の米軍メタブバー基地から陸上自衛隊の不発弾処理部隊が現場に派遣され、爆弾の破片を数個回収した。回収された破片のうち、爆弾の底部の破片に埋め込まれていた起爆装置と思われる部品が確認された。起爆装置は一般的に「時間遅延信管」と呼ばれている。
兵器専門家や戦時中の空襲記録を専門とする研究者は、時限信管付きの500ポンド通常爆弾は、米国のB-29爆撃機やその他の航空機によって、宮崎を含む九州地方や、日本の東部にある関東地方などの他の地域にも投下されたと指摘した。
時限信管の先端にはプロペラ状のブレードがあり、爆弾が落下する際に回転し、スクリュー状のシャフトを下方に駆動させる、と専門家や研究者は説明している。この動きにより、有機溶剤の入ったアンプルが粉砕される仕組みになっている。溶剤が漏れ出し、皿のような形をしたセルロイド栓を溶かす。栓が損傷すると、スプリング仕掛けの起爆針が飛び出し、起爆プライマーを突き刺す。
爆発のタイミングは、おもにセルロイド栓の厚さを調整することで、衝突後1時間から数日の間で調整することができた。それでも、爆発は液体溶剤の化学反応に依存していたため、実際の爆発のタイミングは周囲の温度の影響を受け、想定と異なることも多かった。
宮崎空港は、1943年に旧日本海軍の赤江飛行場として建設され、沖縄戦では特攻基地として使用された。 沖縄戦は、1945年3月26日の米軍による慶良間諸島への上陸作戦で始まった。 同年3月18日の最初の攻撃以降、同飛行場は米軍の空襲の繰り返しにさらされた。
時限爆弾使用の理由について、戦時兵器研究家の山本達也さんは「特攻基地の運用を妨害する狙いがあったのではないか」と推測する。「着弾後に起爆する時間が予測できないため、(空襲被害の)復旧作業を妨害しただけでなく、心理的にもプレッシャーを与えたと考えられる」と話す。
宮崎空港で投下から79年後に不発弾が爆発した理由については、依然として不明であると山本氏は述べた。「考えられるのは、亀裂の入ったアンプルが何らかの振動でさらに損傷したことだ。しかし、不発弾の起爆プロセスがどの段階で止まったのか、あるいは最終的に何が起爆プロセスを再開させたのかを特定するのは難しい」と指摘した。
今回の爆発を受け、国土交通省は不発弾の残存を確認するため、宮崎空港のほか、仙台、松山、福岡、那覇の各空港で地下磁気探査を実施することを決定した。これらの空港では過去にも不発弾が発見されている。
時事通信