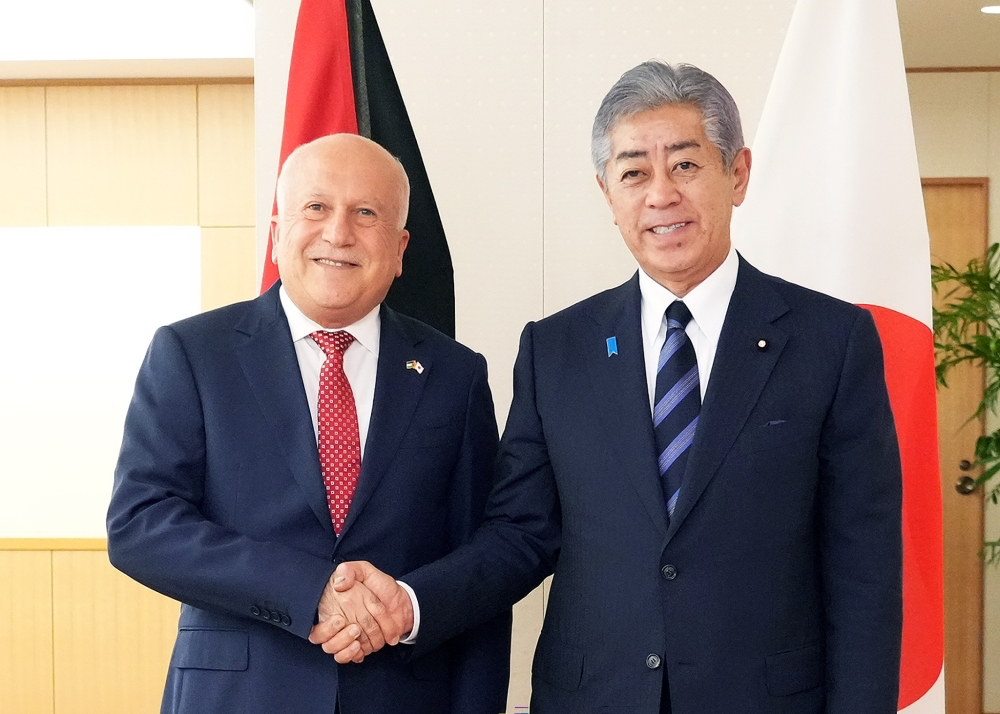- ARAB NEWS
- 01 Aug 2025
サウジアラビアのバーチャル授業、使いこなせるか教師たちも試される

- リモート学習の「新常態」に慣れねばならないのは、幼稚園から大学まであらゆる学校の教師たち
ハラー・ターシュカンディー
【リヤド】新型コロナウイルス感染症の大流行にともなう学校閉鎖を機に、サウジアラビアでは教師たちがオンラインでの授業を始めざるをえなくなっている。その結果、教師たち自身が習熟度を試されることとなった。
教育現場では就学前の段階から大学などの高等教育の段階にいたるまで、教師たちはリモート学習という「新常態」に慣れることを余儀なくされている。中には仮想教室での授業がこの先もずっと続く見通しであることについて、複雑な思いを抱く者もいるのが現状だ。
ビデオ会議のプラットフォーム「Zoom」は、世界を健康危機が駆けめぐりはじめて以来、在宅勤務をする人たちの通信手段としてはもっともポピュラーなもののひとつとなっている。開発元の米テック企業は6月には前年比169%増の収益を上げたと発表、1日あたりのユーザー数は3億人におよんでいる。
Zoom以外のプラットフォームでも、国内外を問わず教育目的での利用が伸びている。
サウジ教育省によるオンライン教育プラットフォーム「マドラサティー Madrasati, مدرستي(私の学校、の意)」では、国内の生徒たちに毎日120時間以上の教育コンテンツを提供している。またYouTubeなどの媒体についても、教育番組にアクセスする者が顕著な増加を見せている。
ZoomやBlackboard、Moodleなどといった学習管理に使われるシステムを導入することで多くの教育者の仕事は便利にはなったとはいえ、対面からネット上の教室への移行まですんなりと進んだわけでもなかった。
メッカ州の高校教師で州内のアル=アブワーで教えているリーハーム・アリー・クトビーさんは、一筋縄では行かなかったものの、いまでは何とか落ち着いた、とアラブニュースの取材に語る。
「新しいやり方で教育を進めるということについては、当初は不安や懸念がありました。ですが、いざ始めてみてコツをつかむようになるといたってスムーズでした。技術的な問題は山ほどありましたけれども、ひとつひとつ乗り越えていったんです」とクトビーさんは語る。
クトビーさんにとっては、新たに出会う生徒たちのことを知っていくことがオンラインで教えるうえでもっとも難しい部分だった、という。
「テストをしたり遠隔授業に参加したりしてもらえば生徒たちの(習熟)レベルはわかるかもしれませんが、一人ひとりがどういう子たちなのかということまではわかりません。生徒たちの趣味だとか関心のあることと教科とを結びつけてより勉強を好きになってもらう、これは私にとっては大変に重要なことなんです」とクトビーさん。
リヤドで高等教育に携わるハイヤー・アッ=スバイイーさんは、オンライン学習にも楽しめるところもあるとはいえ、自分としては対面のほうへぜひ戻りたい、遠隔での授業形態は向いていない、と話している。
「いちばんいいところは、家でくつろぎながら教えられる、というところですね。授業の合間に仮眠を取ったりテレビゲームをしたりもできますし。ところがいちばん悪いところは、その教えることそのものなんです。これは精神的に応えます。授業が終わるたびに神経が張り詰めてイライラしている自分に気が付きますから」
「もうひとつうんざりなのは、学生たちは私のことを年中無休と思っているんですね。メールが止まることはありませんからくたびれてしまいます」とスバイイーさんは言う。
リヤドで大学1年生を教えるサーラ・アル=ハリールさんがアラブニュースに語るところによると、自宅で仕事ができるのは便利ではあるけれども、それをはるかに上回る技術的な問題点がネット授業にはあるのだという。
「自宅から教えられることでいちばんいいのは、便利なことですよね。通勤のことは考えなくていいし、環境にしても服装にしても気が楽になります。でも技術的な問題が起きた場合は最悪になります。どこかの調子がおかしくなると、みんなの時間が無駄になりますしイライラもつのります」
ハリールさんは、学生たちと直接やりとりができないこと、特にちゃんと授業に参加しているのかどうか監視できない点については対応が困難と思っている。
「カメラやマイクをオンにすることを拒否する学生たちなんかもときどきいますから。直接やりとりできないというのはじれったいですね」
今回紹介の先生方は試行錯誤を重ねて数週間。いまだオンライン授業に苛立ちを覚えていたり苦戦したりしている教師たちへ向けたアドバイスがあるのだとか。
「予備の通信手段を確保しておくこと。休み時間用の休憩ルームを活用すること。学生たちをカメラの前に来させてなるべく多くの面で参加させること。それから、一人ひとりの学生の状況だとか通信手段、時間のこともいつも考えに入れること。オンラインでの授業だからって、学生たちが休みなしで講義に出られるわけではありませんし」。ハリールさんはそのように語る。
スバイイーさんのアドバイス。「寛容の精神ですね。それと、学生たちだって自分と同じだけじれったく思っていることを忘れないこと。辛抱と思いやりの精神をもちつづけつつ、自分の心の健康のケアもちゃんとしないといけません」
3人ともリモート学習には効用があることでは意見が一致する。また、コロナ禍が終息してもネット授業には効果が残る可能性がある、という点でも同意見だ。
ハリールさんは言う。「仮想教室というのはいいですね。今までとは違う新しさがありますし、便利だし、それに、復習やプレゼン、それとリスニング技術の教授にも適しています」
「私は、これから先は従来型の授業と仮想型の授業との組み合わせで共存する必要があるのでは、と思っています。授業をどれも実際に出席させておこなう必要もないですし、この点、取り組みを進めて実施に移すべきなんだと思います」
クトビーさんの意見はすこし異なる。ネット授業は役には立つが、対象とすべき生徒を絞るにとどめるべきだと彼女は考えている。「結局のところは、個人的にはもとの対面型の学校教育に戻り、成績面でバックアップの必要な生徒たち向けに遠隔学習を続けるといった形のほうがよさそうだと思っています」