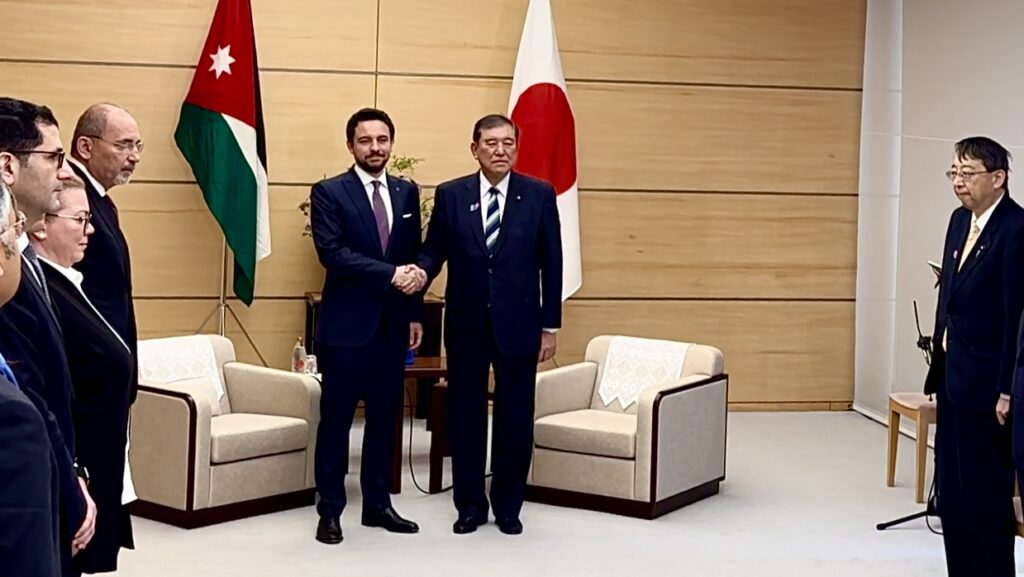- ARAB NEWS
- 31 Jul 2025
- Home
- Article Authors
- アラブニュース・ジャパン
- 日本のガザ外交、曖昧で不明瞭と批判される
日本のガザ外交、曖昧で不明瞭と批判される

東京:日本の外交は「最初から最後まで曖昧だった」と、東京外国語大学教授の篠田英朗氏は述べている。
金曜日の『現代ビジネス』の論評で、篠田氏は日本の「ガザ戦争に対する影響力の欠如」を厳しく批判し、日本の外交が「パニック状態にある」と非難した。
「日本政府のガザ危機に対する態度は、例えばウクライナの状況に対するロシアへの態度や中国に対する明確な態度と比べて、完全に曖昧で不明瞭だ」と篠田氏は言う。「沈黙しているなら、外交には何の意味もない」
篠田氏は他国がガザの人々に対して表明する懸念に言及し、日本には真の共感が欠けていると示唆する。「日本がこれらの感情に共感しないなら、基本的な人間の価値を忘れているようなものだ。基本的な人間の感情の表現を欠き続けるなら、何を言おうと、我々の外交は空虚なままである」
篠田氏は、上川外相の発言が、紛争のいかなる側とも関係を損なわないように冷淡にスクリプト化されていると言う。
日本の弱い外交を批判しながら、篠田氏は米国にも、イスラエルに対して何ら抑制的な影響を及ぼすことができないことについて辛辣な言葉を投げかけている。
「米国の影響力は大いに低下し、その威信は失われた」と篠田氏は書いている。「大規模な軍事支援を提供しているにもかかわらず、イスラエルに対して何ら影響力を行使できていない。トランプの再選を歓迎したいネタニヤフ首相にとって、バイデン大統領は気にする必要のない人物である」
篠田氏は、日本が戦争のいかなる解決にも立場を取ることを避けるために、米国の外交の後ろに隠れようとしている可能性があると示唆する。「要するに、日本が何も気にせずに状況が解決に向かうのを望んでいるのが一番うれしいことである」
しかし、彼は警告する。米国が歴史の間違った側にいるかもしれない場合、「日本は米国の従属国の汚名を引き続き負う準備をするよりも、米国から一定の距離を保つ方が良いだろう」
篠田氏は日本の弱い外交をさらに批判して締めくくる。「日本はガザ危機について米国や、せいぜいG7諸国のような米国の同盟国としか議論せず、他の国々と協力することを避けている。世界中の国々はこの日本の機会主義的な態度を注視している。米国・イスラエルのアプローチの奇跡的な成功を祈るだけでは、外交とは呼べない」