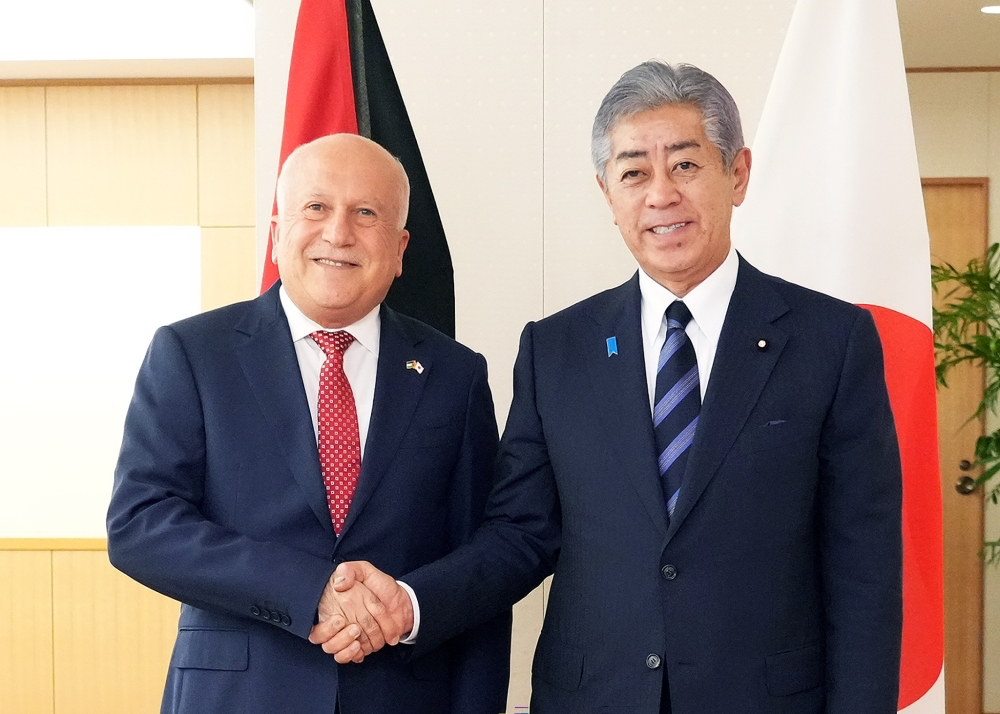- ARAB NEWS
- 01 Aug 2025
ローマ教皇が、自分が派遣されていたかもしれない日本イエズス会を訪問

東京発: フランシスコ教皇は、火曜日の午前中をイエズス会の人々と共に過ごし、ごく私的な時間を過ごして日本訪問を締めくくった。もし、宣教師になるというフランシスコ教皇の夢が実現していたならば、彼はこのコミュニティの一員となっていたであろう。
フランシスコ教皇は、イエズス会が運営する上智大学の礼拝堂で朝のミサを執り行い、引退、および病気療養中の神父を訪問した後、1週間にわたるアジア巡礼の最後の行事となる、イエズス会の教育に関するスピーチを行った。
「現在の日本と同様に、競争力があり、テクノロジー志向の社会の中において、当大学は知性の形成の中心地であるだけでなく、より良い社会とより希望に満ちた未来が形作られる場所であるべきです。」と、教皇は大学の教授陣と学生に対して述べた。
若きアルゼンチンのイエズス会修道士であったホルヘ・マリオ・ベルゴリオ(教皇となる以前の名前)は、16世紀にキリスト教を日本に紹介した聖フランシスコ・ザビエルの足跡をたどることを夢見ていた。
健康上の理由によりその夢が叶わなかった彼は、東京に到着した際、出迎えた日本の司教たちに対し、ブエノスアイレスで大司教を務めていた時に、5人の神父を宣教師として日本に送ることでそのリベンジを果たしたと、冗談を述べた。
その時アルゼンチンから派遣された神父の一人であるレンゾ・デ・ルカ神父は、現在日本イエズス会の管区長であり、フランシスコ教皇の今回の訪日の通訳を務めた
デ・ルカ神父は、彼の神学校時代の学長であったフランシスコ教皇について、とても学生に「寄り添ってくれる」人であり、一時は、100人以上の生徒が神学校に暮らしていたにもかかわらず、常に生徒と接してくれる人だったと述べている。
「当時でさえ、彼を見つけるのは簡単でした。というのも、彼はいつも私たち生徒と一緒に座り、一緒に料理をしていましたから。 時々、私たちのために手料理をふるまってくれたこともありました。」と、デ・ルカ神父はバチカン・メディアに対し語った。 「彼は私たち学生に対して、非常に親しみを持って接してくれた人であり、決して偉い人や 近づきがたい人には、なりたがらなかったのです」。
もし、フランシスコ教皇が宣教師として日本に派遣されていたならば、彼は最終的には、日本の多くのカトリック系の学校と同じような、裕福な家庭の子女が通う名門私立大学である上智大学へと行き着いたであろう。
上智大学でフランシスコ教皇は、長年の友人であるアドルフォ・ニコラス神父と面会した。83歳のアドルフォ・ニコラス神父は、元イエズス会総長であり、30年にわたって神学を教えてきた人物である。 ニコラス神父は最近の健康問題から回復に向かっているところである。
全体的に見て、日本政府からの公的資金で賄われている高等教育でさえも授業料が高く、それらは一般的にエリートたちのためのものとなっている。経済協力開発機構(OECD)のデータによれば、日本の国公立大学で学士号または同等レベルの学位を得るための授業料は、OECD諸国全体では、英国、米国、チリに次いで4番目に高く、年間5,218ドルとなっている。
学生と教授陣に向けたスピーチの中でフランシスコ教皇は、学校がただエリートの中心地であるだけでなく、周囲に取り残されている人々についてもっと考慮するよう、大学に対し求めた。
教皇は、「質の高い大学教育は少数の人々の特権ではなく、常に正義と公共の利益に奉仕するために努力する人々によって満たされるべきである。」として、 「疎外された人々との距離を縮め、断絶を徐々に回復することを目的とした教育的アプローチを実現する努力をすることで、それらの人々は大学生活とそのカリキュラムの中に創造的に組み込まれてゆくでしょう。」と述べた。
また教皇は、自身が優先する課題であり、さらに最近世界中のイエズス会が、その学校、教会、プログラムでテーマとして取り入れるよう明言している、環境に対する懸念についてのカリキュラムをもっと強化するよう大学側に求めた。
学校の外に集まってフランシスコ教皇を歓迎した学生の中には、スペイン語で「ようこそ」と書かれた環境をテーマにした横断幕を掲げた神学部の学生もいた。
学生たちは、教皇は偏見の無い広い心の持ち主で、友達のようであり、非常に親近感を覚えたと語った。
「教皇をとても身近な存在に感じているので、私たちは教皇をパパと呼んでいます。」と、上智大学神学部の学生であるレオ・イトウさんは言う。
ジャーナリズムを学ぶの19歳の学生で、カトリック教徒のヤノ・ツカサさんは、教皇が到着する数時間前に列に並び、教皇に彼の十字架を祝福してもらうことができた。
「完全に圧倒されています。他に言葉が見つかりません。」と、ヤノさんはその十字架を手にのせて見せながら言った。 「教皇は、とても親しみを持って接してくれました」。
AP