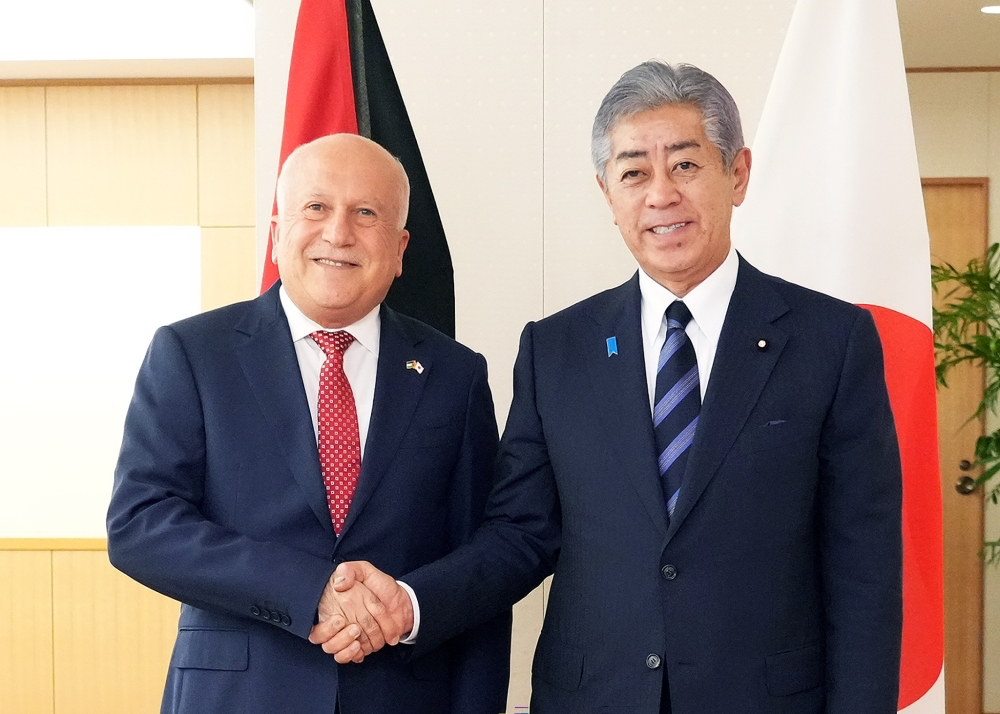- ARAB NEWS
- 01 Aug 2025
日本経済 新型コロナパンデミック以前の水準まで戻るには数年を必要とする

ロイター通信の世論調査によると、今年の日本経済の縮小規模は当初の予測よりも小さくなるものの、、少なくとも2022年初頭までは新型コロナウイルス感染拡大以前のレベルには戻らないだろう。
世論調査では、経済が新柄コロナウイルスのパンデミックによる影響により苦境に陥っている中、日銀の次の政策決定について意見が分かれており、日銀は経済成長を支えるための策を使い果たしたのではないかとの見方が広がっている。
世界第3位の経済大国である日本の来年3月に終了する今年度の経済成長率は、マイナス5.3%となる可能性が高いことが、27人のアナリストによる12月の世論調査で明らかになり、11月に予測されたマイナス5.6%から上方修正された。
上方修正の主な要因は、7-9月期の国内総生産(GDP)のデータが修正され、当初の予想を上回る年率22.9%の経済成長を示し、消費と設備投資が回復したことにある。
新型コロナウイルス対策のための2つの大規模な支出計画に続く、日本の直近の7,080億ドルの景気刺激策もまた、脆弱な経済回復を支えるように設計されている。
HISマークイット社の田口はるみ主席エコノミストは、「外需の持ち直しが加速すれば、回復が加速する可能性がある」と述べ、政府の景気刺激策が企業の消費拡大を促していることを指摘した。
アナリストらは、来年度の景気は11月の調査と同様、3.4%回復すると予想していたが、最近の新型コロナウイルス感染拡大の新たな波の到来により回復が遅れる可能性があると予測している。
調査対象となった40人のアナリストのうち、6人が2021年4月から始まる新年度に日本経済がパンデミック以前の水準に戻ると予想し、15人が2022年度、19人が2023年度以降になると予想した。
住友生命保険の武藤弘明エコノミストは「日本の景気回復のペースは他の先進国に比べて弱い」とし、「潜在的な成長率が低い」と指摘した。
「日本の設備投資は減少傾向にあり、景気が回復軌道に戻るタイミングは海外に比べて遅れる可能性が高い。」
12月3~11日に実施された世論調査において、変動しやすい生鮮食品価格を除いたコア消費者物価は、今年度は0.5%下落し、来年度は0.2%上昇することが明らかになったが、これは前月の世論調査と同様である。
5月以降、日銀は金融政策を安定的に維持してきたが、方向転換を決断した場合、次の政策はどうなるのか、アナリストの間では意見が分かれていた。アナリスト41人中21人が日本銀行によるさらなる金融緩和政策を予想し、20人が日銀は超緩和政策の巻き戻しを開始すると予想した。
東短リサーチの加藤出チーフエコノミストは、「日銀は金融緩和策を拡大又は拡張する可能性はあるものの、当面物価目標の達成に向けた措置を取ることはないだろう」と述べた。
日銀は金曜日に終了する2日間の金利見直しで金融政策を据え置くとの見方が強いが、企業の資金繰りの逼迫を緩和するための様々な措置を来年3月の期限を超えて延長する可能性がある。
ロイター