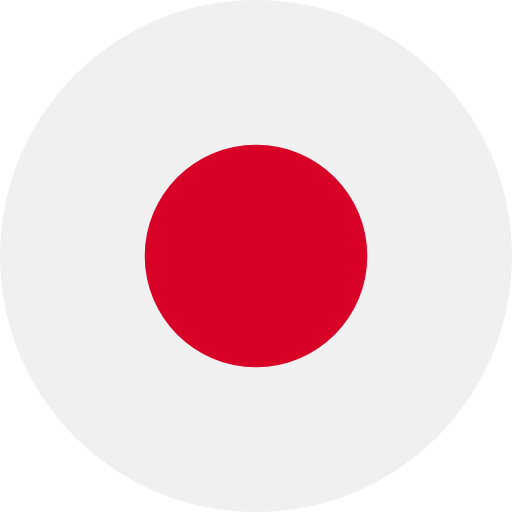- ARAB NEWS
- 30 Jun 2025
日本のオルガン製作者、ノートルダム大聖堂の音色を復元する栄誉に浴す

パリ:関口格氏が初めてパリのノートルダム大聖堂の大オルガンを耳にしたのは10歳の時だった。その「地獄のような音」は彼の人生を永遠に変えた。
「ちょっとしたカルチャーショックでした」と彼は語った。
現在53歳の関口氏は、2019年に起きた火災からの修復を終え、12月7日に再開するノートルダム大聖堂の伝説的な楽器の調律と音色調整を任された数少ない専門家の一人である。
約300年前に作られたこの巨大な楽器は、奇跡的に炎から免れた。
関口氏は、ゴシック建築の傑作の「声」を奏でる機会に恵まれることを夢見て、オルガン製作者兼修復者になるため20代でフランスに移住した。
「フランスでそれが実現できるので、フランスに来たかったのです。でも家族に話したら、ちょっと無謀なんじゃないかと思われたんです」と、東北の仙台出身の関口氏は流暢なフランス語で語った。
2018年、彼は大聖堂の公式オルガン製作者となり、4階建ての建物に相当する高さのフランス最大の楽器の日常的なメンテナンスを担当することになった。
1733年以来、このモニュメントの音を奏でてきたこのオルガンには8,000本のパイプがあり、演奏者たちはその音色をまさに交響曲のような響きと表現する。
「それは私の夢でした。この仕事のおかげで、この楽器をより深く知ることができました」と、コレーズ県中部に四半世紀住んでいる関口氏は語る。
関口氏は、フランスで最も訪問者の多い場所のひとつという制約に適応しながら、オルガンの調律を含むメンテナンス業務を毎月3週間担当した。
「時間は非常に限られていました。夜間に作業しなければならなかったのは、そうしないと観光客に迷惑がかかるからという理由もありますが、調律には完全な静寂が必要だからでもあります」と彼は語った。
しかし、その夢は長くは続かなかった。
その1年後、火災が大聖堂を襲い、関口氏は職を失った。
オルガンは炎から免れ、消防士たちが歴史的建造物の消火に当たった際には比較的少量の水しかかからなかったという事実が、彼にとっての慰めとなった。
「夜の間、何が起こっているのかわからず、矛盾する情報もあったので、オルガンが心配でたまりませんでした。悪夢でした」と彼は語った。
彼は、大きな被害が出たら元に戻すことはできなかっただろうと確信している。
「今日では、同じことはできなかったでしょう」と彼は語った。
火災の直接的な被害は受けなかったものの、楽器は依然として被害を受けていた。
鉛の残留物がオルガンに浸透し、2019年の夏の猛暑で楽器はさらに弱体化した。
2020年12月、オルガンは解体され、専門家の修復作業に送られた。修復作業には3つのオルガン製作工房が関わった。
作業が完了した後、関口氏と他の専門家たちは、再び夜間に作業を行い、楽器の調律と音色調整を開始した。
誰もが関心を寄せるのは、修復を終えた大オルガンがどのような音色を奏でるのか、そして大聖堂が再びその扉を開くのはいつなのか、ということだ。
「正しい音色を出すのは非常に難しい。パイプは1000通りの方法で音を奏でることができる」と、関口氏をプロジェクトに招いたオルガン製作者のオリビエ・シェブロン氏はAFPに語った。
オルガン製作者は、その作業が非常に特殊であるため、自分たちで道具を作り、中には名前のないものもある。そして、彼らのノウハウと主観に頼っている。
「素晴らしいオルガンの音を表現するのは難しい」と、2000年代初頭に関口氏を雇ったオルガン製作者のベルトラン・カティオ氏はAFPに語った。
「私にとって、それは大聖堂の音色を反映している」と、長年ノートルダム大聖堂の大オルガンのメンテナンスを担当していたカティオ氏はいう。
関口氏もまた、オルガンの音色を再現するために記憶を呼び起こしている。
膨大な作業ではあるが、フランスを象徴するこの建造物の修復に携わる機会を喜んでいる。
「多くのこと、多くの名誉、そして多くの作業と責任があります。信じられないことです」と彼は語った。
AFP