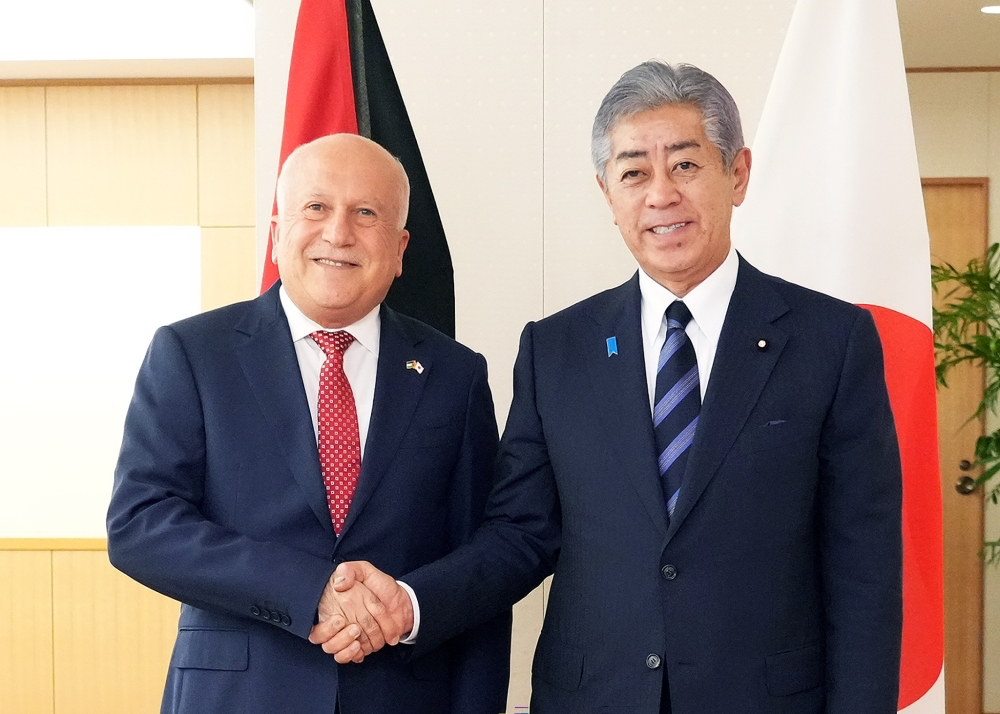- ARAB NEWS
- 01 Aug 2025
「企業努力に幸運重なる」=中越地震で新幹線脱線、死傷者ゼロ-畑村東大名誉教授

営業運転中に初めて新幹線脱線事故が起きた新潟県中越地震から15年が過ぎた。当時、独自に現地調査を行った畑村洋太郎・東京大名誉教授(78)が、2日までに時事通信の取材に応じ、「安全神話の崩壊」など批判的な声が上がったことについて、JR東日本は現場の耐震補強工事を地震前に自主的に行ったと指摘。死傷者が出なかったことを「企業の愚直な努力の上に幸運が重なった」と評価した。
地震は2004年10月23日午後に発生した。上越新幹線「とき325号」が浦佐-長岡間の高架橋を時速約200キロで走行中に脱線したが、橋が倒壊せず、車輪と車体の部品が偶然レールを挟み込んだため転落や転覆を免れた。乗員乗客154人は無事だった。
1995年の阪神大震災後、国はJR各社に対し、大規模な地震が来ると予想される地域での緊急耐震補強工事を指示していた。中越地方は対象外だったが、JR東日本は自主的に新幹線の線路に近接する活断層を調査した。
畑村氏などによると、同社は国が指示した地域と自主的に選んだ地域で、倒壊する恐れがある計約3000本の橋脚の補強工事を計画。中越地震の際、とき325号が走っていた高架橋も含まれており、98年度末までに工事を終えた。同氏は「高架橋が崩れていたら、(新幹線が)突っ込んで全員即死だった。持てる知識を全て使い、計算して何が起こるか考え、計画を立てて実行すると人の命を救える」と強調した。
畑村氏は東京電力福島第1原発事故で政府の事故調査・検証委員会の委員長も務めた。「最後には技術的な問題ではなく、組織で働いている人間の価値観が問題になる。東電経営陣は(大津波を予想した)データを信用せず、何もしなかった」と述べた。
一方、日本では事故原因の究明より、個人の責任追及に比重を置いていると批判した。米国では原因究明に向け、当事者の証言を得やすくするため、個人の責任を問わないことが原則とされる。畑村氏は「社会の制度と考え方を変えないといけない。お前が悪いという部分で争うことに何の意味があるのか」と話した。
Jiji Press