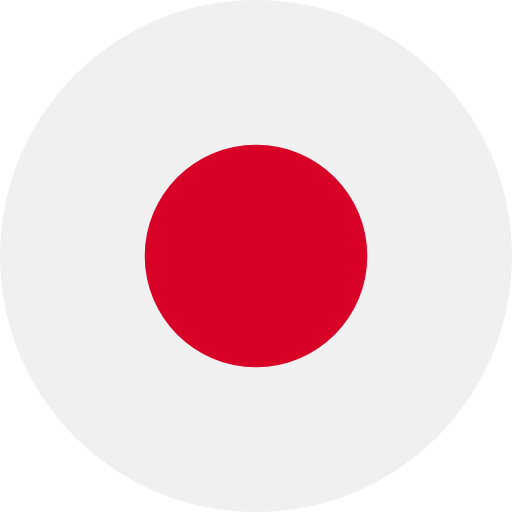- ARAB NEWS
- 03 Jul 2025
「人生の窓が開いた」=バリアフリーに驚き―64年出場選手ら

障害のあるアスリートが競い合うパラリンピック。前回の東京大会が開かれた1964年は、障害者が外出することも珍しい時代だった。車いす対応の選手村や海外選手の振る舞いに当時の選手らは驚き、「パラのおかげで人生の窓が開いた」という。
高知県安芸市のNPO役員近藤秀夫さん(86)は、16歳の時に炭鉱事故で負傷。車いす生活となり、大分県内の障害者施設に入った。
スポーツと言えば施設にあった和弓(わきゅう)ぐらいだったが、「日本パラリンピックの父」と呼ばれる医師の故中村裕さんに誘われ、パラアーチェリーなどへの出場が決まった。
ワゴン車や飛行機を使って上京したが、車いすでは利用できなかった。「おんぶしてもらわないといけなかった。本音では嫌だった」と苦笑する。
大会では「撃った矢がどこに飛んだか分からない」ような結果だったが、選手村での生活は驚きの連続だった。車いすのまま乗れるバスやスロープ、洋式トイレがあり、「街がこういう形なら僕らは施設を出られるのに」との思いを強くした。
通訳派遣会社「バイリンガル・グループ」(東京都新宿区)社長の郷農彬子さん(78)は、パラの通訳ボランティア「語学奉仕団」の一員だった。
当時は「障害者を見てはいけない、見たら相手に悪いと思っていた」。ただ、選手村の交流スペース担当になり、会話や歌を楽しむ海外選手と触れ合ううち、「みんな自分に自信を持っている。臆することはない」と考えを改めた。
「パラのおかげで人生の窓が開いた」という近藤さんは、その後東京都町田市職員になり、建築物のバリアフリー化に取り組んだ。郷農さんも車いすバスケ大会で通訳を受け持つなど、障害者スポーツとの関わりは続く。
パラリンピックの自国開催は57年ぶり。この間、障害者を取り巻く環境は大きく変わったが、共生社会の実現は道半ばだ。近藤さんは「障害があることはマイナスではなく、高度な表現もできることを知ってもらえたら」と話した。
時事通信