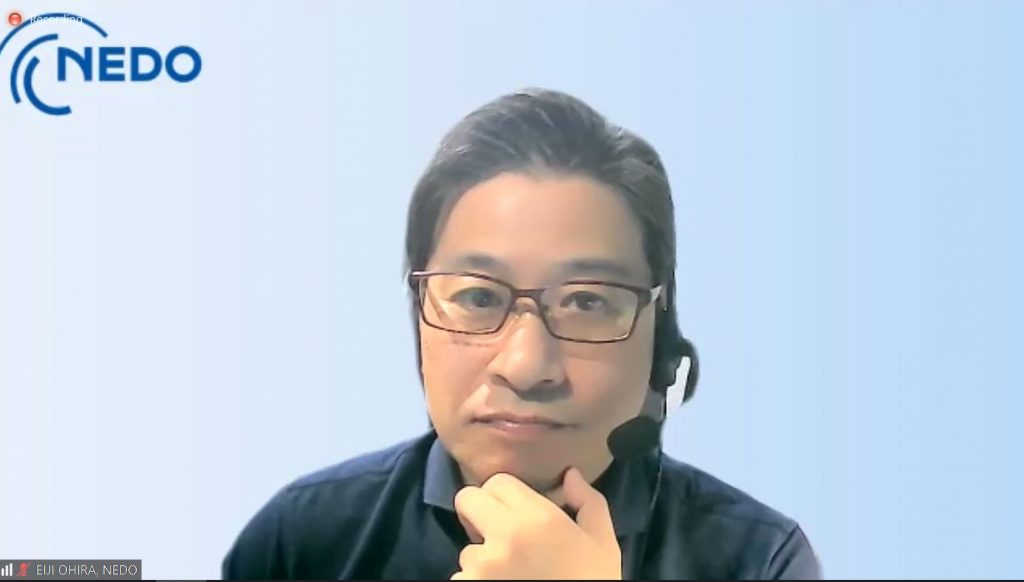


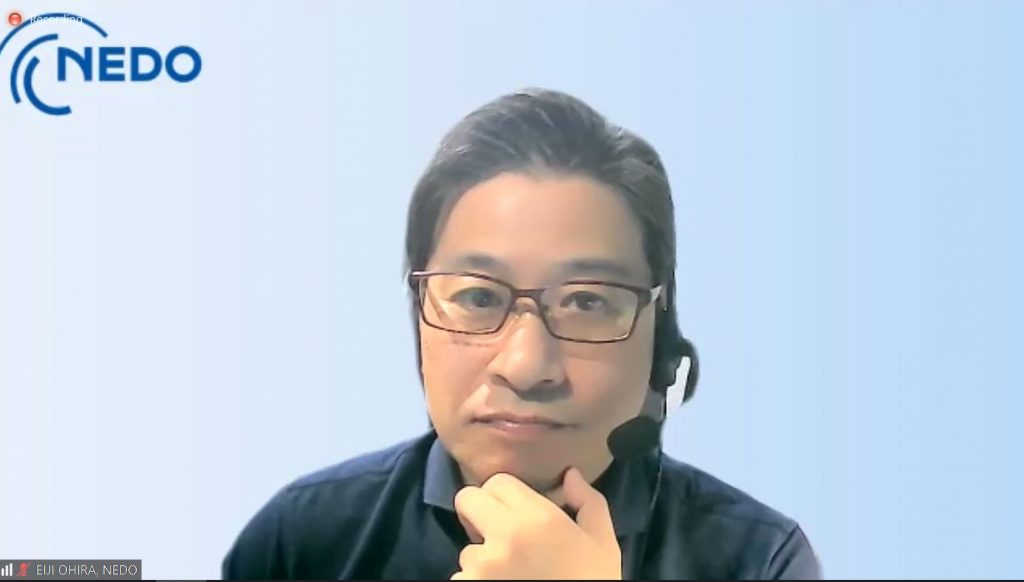


アラブニュース
2月3日にオンラインフォーラムが開催され、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)燃料電池・水素グループの大平英二室長が、水素製造の研究開発について講演を行った。
フォーラムではまず、大平室長が自己紹介とともに、日本における水素・燃料電池の展望についてプレゼンテーションを行った。
「水素社会はすぐには実現しない」と述べ、時間がかかるだろうと大平室長は話した。
大平室長は、NEDOの取り組みを紹介し、同機構が水素の普及を確実にするために、燃料電池の市場への導入から始まり燃料電池自動車の導入へと段階を踏んできたことを説明した。
さらに、東京から約250km離れた場所にあり、東芝エネルギーシステムズ株式会社を含む5つの主要プロジェクトメンバーで構成される「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」についても触れた。
同施設は、20MWの太陽光発電設備や、水を電気分解して水素を製造する水電解システム、水素貯蔵や供給設備など、様々な要素で構成されている。
2020年3月に開所した同施設では、再生可能エネルギーを利用して毎時1,200Nm3もの水素を製造することができる。FH2Rで製造された水素は、主に福島県内で使用するために輸送・供給される。
大平室長は、水素はカーボンニュートラルのためのキーテクノロジーであり、持続可能な開発の鍵となると強調した。
また、水素がさまざまな資源から製造できること、温室効果ガスを排出しないこと、貯蔵・輸送・輸出が可能であることなどのメリットも説明した。水素はさまざまな分野で利用されていることもあり、日本は水素を強力に推進している。
この推進策は、2050年までに温室効果ガスの排出を正味ゼロに削減するという日本の大きな目標に沿ったものだ。
大平室長は、水素の利用が進んでいる様子を例示し、日本には2021年9月時点で家庭用燃料電池が41万台、乗用車が6,500台、水素ステーションが160ヶ所あると述べた。
このことは、2017年に17社から始まったCEO主導のグローバルな取り組みである「水素協議会」が134社にまで拡大したことでも示されており、発展ぶりを強調するものだと大平室長は述べた。