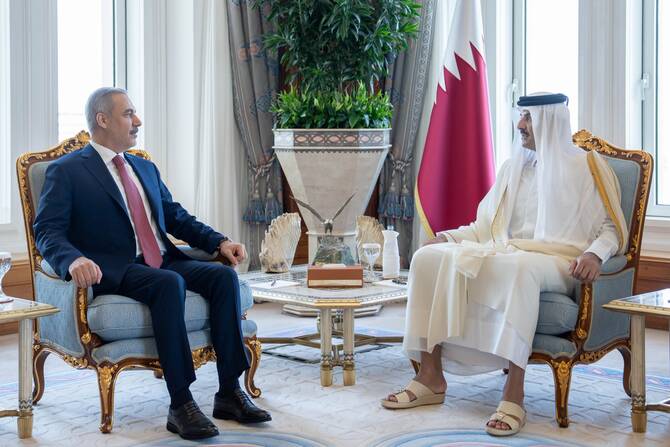- ARAB NEWS
- 16 Aug 2025
トルコ人とシリア難民間の分断が広がる傾向 調査で浮き彫り

- 調査では、シリア人回答者の51.8%が帰国は考えていないとの結果も
メネクシェ・トキャイ
アンカラ:トルコのシリア難民たちにとって、現地の社会に溶け込めるかという問題は深刻さを増している ― 広範囲にわたり行われた最新の調査では、最大85%のトルコ人がシリア難民たちにはトルコ人の居住区域から離れて住んでほしいと望んでいるという結果が示されているのだ。
調査を主導したイスタンブールのトルコ・ドイツ大学のムラート・エルドアン教授によると、戦争で荒廃したシリアから最初の難民たちがやって来てからほぼ10年が経過しているものの、シリア難民は依然として受け入れ側のトルコ人たちに否定的に見られているようだ。
「難民たちに適切な生活水準を与えるよう努力して、こうした二極化の傾向を緩和しなければ、政治的な緊張関係やヘイトスピーチによって彼らのトルコ社会への統合はさらに難しくなってしまうでしょう」とエルドアン教授は警告する。
今回の調査「シリアバロメーター2019」の結果詳細は来る水曜日に発表される。トルコ人たちとシリア人たち双方へのインタビューを含むこの調査は、トルコの国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の支援を受けて実施された。
トルコには一時的保護を受けている360万人以上のシリア人が住んでおり、来年にはさらに100万人の難民が到着すると予想されている。
今回の調査結果には、トルコ人回答者の60.4%がシリア人と同じ建物に住むことを拒否し、52%が自分の子供がシリア人と一緒の学校に通うことを望まず、56.3%がシリア人との仕事を避けたがっている、等の内容が含まれている。
しかし、トルコ人たちがシリア難民を文化的にも社会的にも遠い存在と見ているのとは対照的に、シリア難民たちはトルコ人を自分たちによく似た人々と信じている。
シリア難民たちにとっての最大の問題は、調査によれば貧弱な雇用条件であり、36.2%が職場で深刻な問題を経験している。
トルコに住むシリア人の約70%は、違法な形で働いているものと見られている。
調査では、トルコ人回答者のほぼ80%近くが、ほとんどのシリア難民たちがこの国に永住するだろうと見ている一方、60%が難民問題をトルコの抱える「3番目に深刻な」問題として挙げている。
エルドアン教授によると、トルコ人とシリア人の間の分断は着実に広がっているという。
「2014年には、シリア難民を遠い存在と感じていたのは回答者の70%でしたが、その割合は2017年には80パーセントに増加し、今回は82パーセントに達しています」と教授はアラブニュースの取材に対して語った。
エルドアン教授は、難民受け入れの規模の大きさが、シリア人が難民たちの社会への統合に苦労している背後にある重要な要因だと言う。
「例えば在トルコのイラン難民については、その数が5万人をわずかに超える程度であるため、誰も心配していません」と教授は指摘する。
しかし、調査では受け入れ側であるトルコ人たちからの難民への嫌悪感が浮き彫りにされた一方、在トルコのシリア人たちの半数は幸福を感じているのだ。
「一見、それは矛盾しているように見えます。ですが、シリア人たちは閉鎖的なコミュニティの中で生活しており、独自の「幸せと粘り強さの領域」を築いているということなのです」とエルドアン教授は説明する。
今回の調査では、シリア人回答者の51.8%がシリアへの帰国を検討していないことも判明した。今までのところ、トルコ軍が管理するシリア北部の安全な地域に自発的に戻ってきた難民は、40万人にすぎない。
エルドアン教授は、難民たちを社会に溶け込ませる取り組みを成功させるには、トルコの政治的および社会的な緊張を緩和するための全国的な戦略が必要であると指摘する。
アンカラを本拠地とするシンクタンク・TEPAVの移住政策アナリスト、オマール・カドキョイ氏は、シリア人たちのトルコ語能力の低さが、彼らの社会的な活動や交流を妨げていると見ている。
「シリア人たちのトルコ語能力の不十分さは、シリア人とトルコ人の共存を育む国家戦略の欠如を反映したものでもあります」とカドキョイ氏はアラブニュースに語った。
多くのシリア人がトルコ永住を計画している状況を受け、カドキョイ氏は、2014年以来政策立案者たちが約束している「調和政策」を、トルコ政府が強化すべきだと考えている。
カドキョイ氏はまた、所得水準に関係なく、多くのトルコ人たちが、シリア難民がトルコの経済的問題の原因だと信じている、とも指摘した。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行は、シリア人の方が景気の後退に対してより脆弱であることを示している。無給休暇を強制されたシリア人の数は同様のトルコ人の3倍にのぼっているのだ。
「失業したシリア人はトルコ人の4倍以上です。これは主に、シリア人の雇用がインフォーマルなものであることが原因です」とカドキョイ氏は言う。
労働許可関連の諸規則の枠組み内で、シリア人の労働者の権利はより強力に保護されなければならない、とカドキョイ氏は付け加えた。