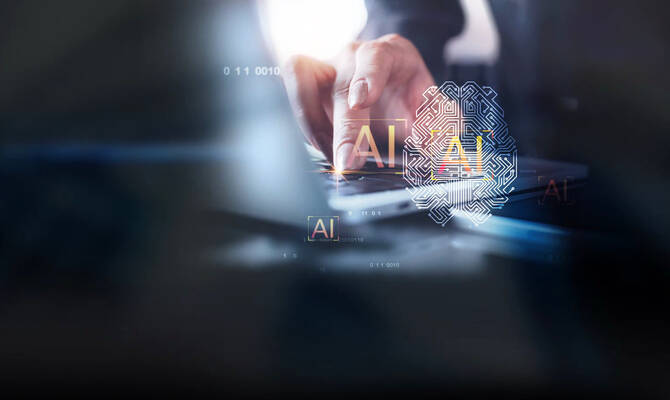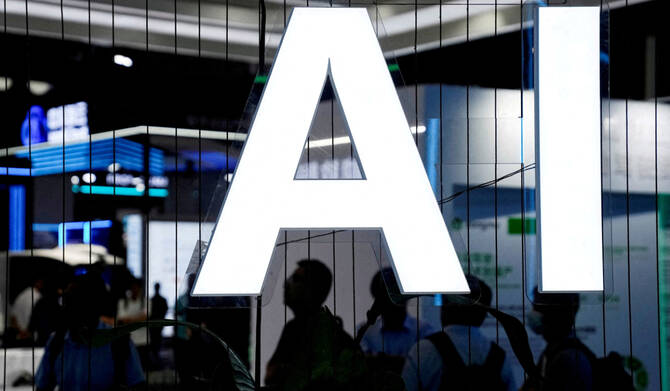
- ARAB NEWS
- 20 Aug 2025
AIソフトパワーの時代
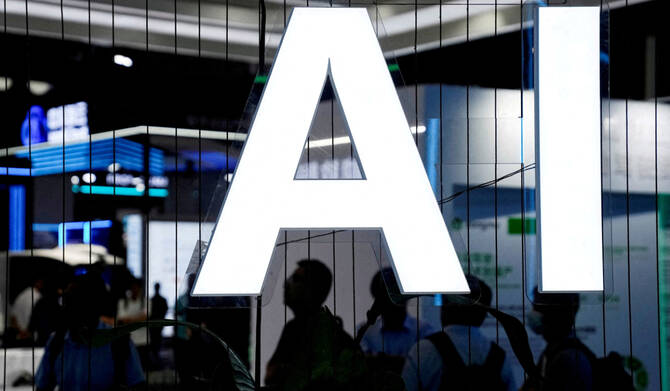
オープンAIやディープマインドのような人工知能のリーダーたちは、人工的な一般知能、つまり人間ができるあらゆる知的タスクを実行できるモデルを構築する競争をしていると考えている。同時に、米国政府と中国政府は、AI競争をマンハッタン計画を彷彿とさせる巨額の投資を必要とする国家安全保障上の優先事項とみなしている。どちらの場合も、AIは、膨大な計算資源とそれを経済的・軍事的優位に変える手段を持つ超大国のみがアクセスできる、新しい形のハードパワーと見なされている。
しかし、この見方は不完全であり、ますます時代遅れになっている。中国のディープシーク社が今年初めに低価格で競争力のある性能のモデルを発表して以来、私たちは新しい時代に突入した。最先端のAIツールを構築する能力は、もはや一部のハイテク大手に限られたものではない。高性能のモデルが世界中で複数登場し、AIの真の可能性はソフトパワーを拡大する可能性にあることを示している。
大は小を兼ねるモデルの時代は2024年に終わった。それ以来、モデルの優劣は(増え続けるデータとコンピューティング・パワーに基づく)規模だけで決まるものではなくなった。ディープシークは、莫大な資本がなくてもトップクラスのモデルを構築できることを証明しただけでなく、高度な開発技術を導入することで、世界的にAIの進歩を根本的に加速できることも証明した。「AI民主化のロビン・フッド」と呼ばれるディープシークは、オープンソース化を決断し、イノベーションの波を巻き起こした。
ほんの数カ月前のOpenAIの独占状態(あるいは数社による寡占状態)は、多極化した競争の激しい状況へと変化した。中国のアリババ(Qwen)とムーンショットAI(Kimi)も強力なオープンソースモデルをリリースしており、日本のサカナAI(私の会社)もAIイノベーションをオープンソース化している。米国の巨大企業メタは、オープンソースのラマ・プログラムに多額の投資を行い、他の業界リーダーからAI人材を積極的に採用している。
最先端のモデル性能を誇るだけでは、産業用途のニーズを満たすにはもはや十分ではない。AIチャットボットを考えてみよう。一般的な質問には「70点満点」の回答を返すことができるが、融資の審査から生産スケジューリングに至るまで、専門家の間で共有される集合的なノウハウに大きく依存するほとんどの実世界タスクに必要な「99点満点」の精度や信頼性を達成することはできない。基礎モデルを特定の用途から切り離して考える古い枠組みは限界に達している。
DeepSeekは、高度な開発技術を導入することで、世界的にAIの進歩を根本的に加速できることを証明した。
伊藤 錬
現実世界のAIは、相互に依存するタスク、あいまいな手順、条件ロジック、例外ケースなど、緊密に統合されたシステムを必要とする厄介な変数を処理しなければならない。従って、モデル開発者は特定のアプリケーションの設計により多くの責任を負わなければならず、アプリ開発者は基礎技術により深く関与しなければならない。
このような統合は、地政学の将来にとっても、ビジネスと同様に重要である。これは「主権AI」という概念に反映されており、国家のAI自律性の名の下に、外国の技術サプライヤーへの依存を減らすことを求めている。歴史的に米国外では、検索エンジン、ソーシャルメディア、スマートフォンといった重要なインフラをシリコンバレーの巨大企業にアウトソーシングすることで、持続的なデジタル貿易赤字が発生することが懸念されてきた。AIが同じ道をたどれば、経済的損失は指数関数的に拡大する可能性がある。さらに、海外から調達したAIインフラをいつでも停止できる「キルスイッチ」を心配する声も多い。こうした理由から、現在では国内でのAI開発が不可欠と見なされている。
しかし、主権を持つAIとは、すべてのツールを国産化することを意味する必要はない。実際、コスト効率やリスク分散の観点からは、世界中のモデルをミックス&マッチする方がまだ良い。ソブリンAIの真の目標は、単に自給自足を達成することではなく、他国が自発的に採用したくなるようなモデルを構築することで、AIのソフトパワーを蓄積することにあるはずだ。
伝統的にソフトパワーとは、民主主義や人権といった思想、ハリウッド映画のような文化的輸出品、最近ではフェイスブックのようなデジタル技術やプラットフォーム、あるいはもっと微妙なところでは、日常的な習慣を通じて文化を形成するWhatsAppやWeChatのようなさまざまなアプリの魅力を指してきた。多様なAIモデルがグローバルに共存するようになれば、最も広く採用されるAIモデルは、人々の日常的な意思決定に組み込まれることで、微妙ながらも深遠なソフトパワーの源泉となるだろう。
AI開発者の観点からは、一般大衆に受け入れられるかどうかが成功の鍵を握る。多くの潜在的なユーザーは、強制、監視、プライバシー侵害などのリスクを認識しているため、すでに中国のAIシステム(米国のシステムも同様)を警戒している。将来、最も信頼できるAIだけが政府、企業、個人に全面的に受け入れられることは容易に想像できる。日本と欧州がそのようなモデルとシステムを提供できれば、グローバル・サウス(南半球)の信頼を得ることができるだろう。
信頼に足るAIとは、単にバイアスを排除したり、データ漏洩を防いだりすることではない。長い目で見れば、AIは人間中心の原則を体現するものでなければならない。AIが富と権力を少数の手に集中させることになれば、不平等が深まり、社会的結束が損なわれることになる。
AIの物語は始まったばかりであり、勝者総取りの競争になる必要はない。しかし、高齢化が進む北半球でも、若さあふれる南半球でも、AIによる不平等が永続的な分断を生む可能性がある。このテクノロジーが、蔓延する支配の道具ではなく、信頼されるエンパワーメントの道具となるようにすることが、開発者自身の利益となる。
– 元外交官の伊藤錬氏は、サカナAIの共同設立者である。©Project Syndicate