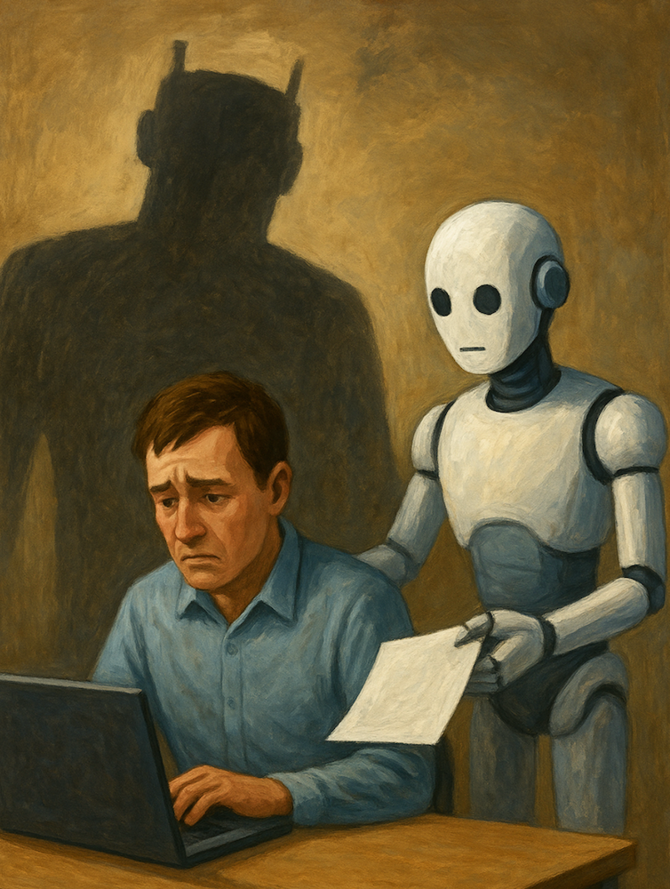
- ARAB NEWS
- 25 Aug 2025
- Home
- 意見
- ジョン・スファキアナキス博士
- AI、仕事、そして雇用の未来
AI、仕事、そして雇用の未来
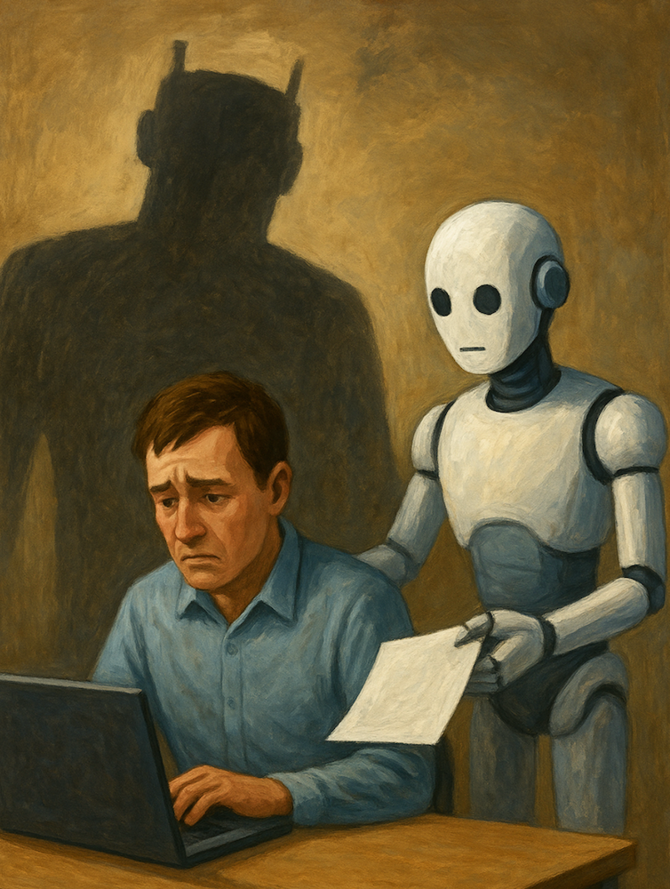
2世紀にわたり、技術革命は激変と再生の両方を約束してきた。紡績機械はギルド制度を崩壊させ、トラクターは農場労働者を追い出したが、何百万人もの人々を養い、コンピューターは事務作業を空洞化させる一方で、産業全体を生み出した。技術革新の波が押し寄せるたびに、大量失業に対する不安はかき立てられたが、そのたびに、新たな分野が離職者を吸収していった。
しかし、人工知能は違う。織機やトラクターとは異なり、AIは肉体労働だけでなく、契約書の作成や病気の診断、さらにはソフトウェアの作成といった認知的な仕事までも脅かす。2025年に政策立案者が直面する問題は、もはやAIが労働市場を再編成するかどうかではなく、機械が思考を行うようになった後も人間がどこで雇用を見つけるかということだ。
変化のスピードは尋常ではない。2022年のChatGPTのデビューに続き、2024年にはグーグルのGenie 3が登場した。2025年にリリースされたGPT-5は、推論のフロンティアをさらに押し進めた。これらはニッチなツールではない。それ以前の産業革命が経験したことのないスピードで普及する汎用技術なのだ。数千万人の雇用が失われ、世界中で数億人が自動化される可能性があり、アメリカではすでにパンデミック以来最高の解雇者数となっている。
調査によれば、米国企業の半数近くがAIのために人員削減を見込んでいるという。国際労働機関(ILO)の推計によると、世界全体の14%の仕事が自動化のリスクにさらされており、さらに32%が大きな変化を遂げる可能性がある。ゴールドマン・サックスは、全世界で3億の雇用が失われる可能性があるとしている。この大変革はもはや仮説ではなく、進行中である。
歴史は先例を示してくれるが、必ずしも慰めにはならない。繊維機械を破壊したラッダイト運動は間違っていたことが証明され、コンピューター革命はタイピングプールをなくしたが、まったく新しい産業を生み出した。しかし、今日の類推は難しい。それ以前の技術革新は、鉄鋼、自動車、ITなど、新たな産業のフロンティアを切り開く一方で、手作業や事務的な仕事を置き換えた。対照的に、AIは認識そのものを自動化する。トラクターが農民を工場に移動させたとしたら、契約書が自分で書かれるようになったら弁護士はどこに行くのだろうか?今回は、長い間自動化には強いと考えられてきた専門職クラスでさえも危険にさらされている。
各国政府は躍起になっている。シンガポールはAI関連の再教育に資金を投入している。EUは、労働者が部門を越えてシフトできるよう「スキル・パスポート」を試験的に導入している。米国では、かつては縁の下の力持ちだったベーシックインカムが主流となりつつある。しかし、これらの努力は断裂の継ぎ接ぎのように感じられる。マッキンゼーは、AIが2040年までに世界経済に年間4兆4,000億ドルの生産性をもたらすと予測している。このままAIが進化し続ければ、事務員やパラリーガルだけでなく、放射線技師やアナリスト、さらには教師までもが置き去りにされ、中産階級の基盤が揺らぐことになるだろう。
地政学的な背景も緊急性を高めている。最先端のAIシステムを育成するのは非常に資源を必要とするため、競争できる国や企業は限られている。競争相手はアメリカと中国の巨大企業に絞られている。AIへの世界の民間投資は2024年に670億ドルに達し、米国がその約半分を占める一方、中国は2030年までに1500億ドル以上のAI支出を約束している。
米国ではAI関連分野の大学院生の70%が外国生まれであり、中国が最も優秀な人材を提供している。アメリカにおけるAI博士号の約30%は中国人が占めている。中国からの移民は、米国の最も重要なAI企業48社のうち8社を設立し、メタ社の「スーパーインテリジェンス」チームの半分は中国人である。しかしワシントンはH-1Bの抽選を厳しくし、エリート大学が外国人の才能に頼っていることを非難している。アメリカがグローバルな頭脳を最も必要としているまさにその時に、彼らを締め出そうとしているのだ。皮肉なものだ。中国にAI競争で負けることを恐れている国が、その優位性を支えている中国のエンジニアや起業家を遠ざけているのだから。
今日のフロンティアAI研究は、開かれた分野ではなく、厳しい門に囲まれた領域であり、資金よりも、最先端を推進できる人材の希少性に制約されている。この比較は、消費者向けテクノロジーというよりも、ブレークスルーが数少ない研究室に集まった一握りの頭脳にかかっていた初期の原子物理学に似ている。
このままAIが進歩し続ければ、放射線科医やアナリスト、さらには教師までもがAIに取って代わられ、中流階級の基盤が揺らぐことになるだろう。
ジョン・スファキアナキス博士
最大手のテクノロジー企業にとっては、何十億ドルもの資金を費やしても、本当に重要な研究者の数は数百人に過ぎない。
しかし、中心的な不確実性は、誰が競争をリードしているかということだけでなく、競争がどこに向かっているのかということである。AIと生産性に関する文献は、証拠が乏しいだけでなく、AIそのものがどのような方向へ向かうのかがまだわかっていないため、不安定なままなのだ。経済を飽和させる新たな電力になるのか、それとも過剰に誇張されたツールになるのか。その軌跡が明らかになるまでは、AIの長期的影響に関する自信に満ちた主張はどれも、科学的というよりは推測に過ぎない。
例えば、高齢者ケア、ホスピタリティ、コミュニティサービス、工芸品など、信頼、共感、物理的な存在が不可欠な分野に人間がシフトしていくと主張する人もいる。また、合成生物学や宇宙探査のようなまったく新しい産業に期待を寄せる人もいる。しかし、そのような代替案は投機的であり、何千万人もの離職者を同等の賃金で吸収できる可能性は低い。経済協力開発機構(OECD)は、AIによる自動化は中産階級を空洞化させる可能性が高く、社会の安定を維持する中技能職に不釣り合いな影響を及ぼすと警告している。
さらに不安な可能性は、社会が恒久的な構造的失業を受け入れ、労働よりも再分配に頼るようになることだ。労働の社会的役割が低下したとき、社会はまとまることができるのか。そしてもっと深い問題として、かつて私たちの種を定義していた「考える」という作業そのものがアウトソーシングされたとき、人類はどうなるのだろうか。これは単に経済的な問題ではなく、文明の謎である。誰かが、あるいは他の何かが、自分たちの代わりに思考をするようになったら、人々はどうするのだろうか?
国民の不安はこの不確実性を反映している。最近のピュー調査によると、アメリカ人の62%が20年以内にAIが仕事に大きな影響を及ぼすと予想しているが、仕事の機会を改善すると考えているのは28%に過ぎない。言い換えれば、ほとんどの人は混乱が起こると見ているが、その恩恵を受けられると期待している人はほとんどいないということだ。この不安は見当違いではなく、すでに進行中の変化の規模を反映している。
政策立案者は、この問題に取り組み始めたばかりである。ベーシックインカムや負の所得税による再分配が打撃を和らげる可能性はあるが、納税者がそのようなプログラムを維持するかどうかは不透明だ。機械が労働者を置き換えるのではなく、むしろ補強するような人間とAIのコラボレーションは、浸食を遅らせることはできても止めることはできないだろう。さらに急進的なのは、「仕事」そのものを再定義することである。介護やボランティア活動、AIでは完全には再現できない創造的な追求にまで認識を広げることだ。しかし、これには経済的価値や社会的地位の再構築が必要であり、それを行おうとする政府はほとんどない。
利害関係はこれ以上ないほど大きい。AIはすでに大恐慌以来のペースで雇用を奪っている。蒸気機関、電気、コンピューターは経済を再構築したが、認知領域では人間の優位性を維持した。今回、機械は工場の現場だけでなく、机の上にもやってくる。
清算は避けられない。適応する社会は、セーフティネットを構築し、人間とAIの補完性に投資し、新産業を育成することで移行を乗り切ることができるだろう。しかし失敗した社会は、大量の失業と政治的不安を抱えることになる。AI革命は私たちに、どのような仕事が残るのかだけでなく、機械が私たちを凌駕したとき、仕事そのものの尊厳が生き残ることができるのかという、より鋭い問題を突きつけている。
課題はもはや、機械と歩調を合わせることではなく、機械に先を越されることが必至となったときに、私たちがどのような社会を望むのかを決めることなのだ。
- ジョン・スファキアナキス博士はガルフ・リサーチ・センターのチーフ・エコノミスト兼経済調査部長。























