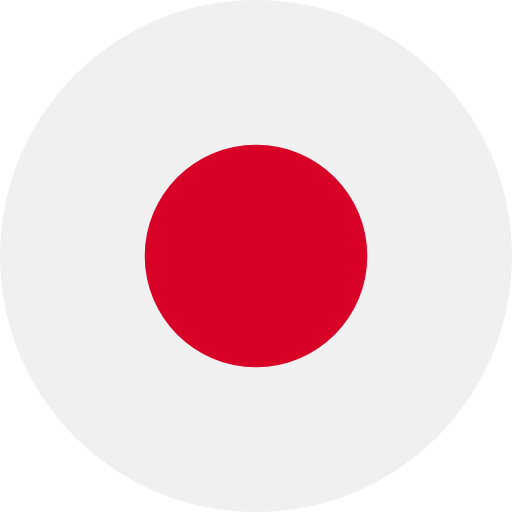- ARAB NEWS
- 21 Aug 2025
広島の10代たちが、アートで原爆の恐怖を伝える

広島:1945年、アメリカによる原爆投下から4日後の広島の廃墟を歩き回る5歳の平中雅樹さんは、母親の手を握りしめ、彼女を守ることを静かに誓った。
これは、80年前の8月に起こった多くの光景の一つで、80歳になった今も平中さんの記憶に刻まれている――そして今、日本の高校生たちによってキャンバスに鮮やかに描かれている。
広島の基町高校は、ほぼ20年にわたり、美術部の生徒たちに被爆者(原爆生存者)へのインタビューを課し、その衝撃的な証言を絵画に表現させてきた。
8月6日の記念日を前に、同校が最近展示した15点の新たな作品には、焼けた兵士が苦痛に悶える姿や、炎に包まれた恐怖に震える少女の姿などが描かれている。
「この絵は、当時の私の気持ちをとても正確に表現していると思う」と、広中さんは「私の人生で忘れられない一ページ」を不朽のものにしたその作品の前で、満足そうにうなずきながらAFPに語った。
「本物で、とてもよく描かれている」と。
女子学生の高砂ハナさんの感動的な作品は、1945年8月10日、広島の廃墟を歩きながら母親を見上げる若い広中さんを描いている。
数日前、爆風で重傷を負った父親が帰宅し、肉に深く刺さったガラス片を引き抜くよう広中さんに頼んだ。
父親はその後間もなく死亡した。
未亡人となった母親は、広中さんの小さな手を握りしめ、背中に幼い妹を背負いながら、彼に不安を呟きながら下を向いている。
「その瞬間、私は彼女を助けて支えたいという強い決意に駆られました。それがこの絵に表現されています」と広中さんは語った。
広島に投下された「リトルボーイ」原爆は、放射能による死者を含む約14万人を殺害した。
基町高校は、当初広島平和記念博物館の取り組みの一部として設立され、現在ではその一環として、200点を超えるアート作品を生み出してきた。
その目的は、原爆の記憶を若い世代に伝え続けることだ。
ここ8カ月ほど、広中さんをはじめとする被爆者たちが数週間おきに生徒たちと一緒に作品を見直し、時には大幅な修正を指示した。
「最初は広中さんとそのお母さんをまっすぐ前に向けて描いたのですが、前を向いていると、そのときの彼女の葛藤が表現できないと広中さんに指摘されました」と、高砂さん(17)はAFPに語った。
「これらの描写された場面を実際に目にしたことがないため、私の表現が正確かどうか自信がなかった」と、学校の散らかった美術室で彼女は語った。
同じように、16歳のオノウエ・ユメコさんの作品は、広中さんが放射能を含む「黒い雨」で煤に覆われたカボチャを描いたものだ。
当初、果物の葉を活力に満ちた上向きの姿で描いたが、広中さんの記憶に合わせるため「完全に描き直してしおれた姿にした」と述べた。
「当時の写真はほとんどが白黒だったのですが、絵画は色を加えることによって、重要な要素を強調できるため、意図したメッセージを表現するのに適していると思います」とオノウエさんは語った。
これらの若者の多くは想像力を頼りにし、歴史的資料を調べた。
惨状に浸ることは、本田メイさん(18歳)のような一部の人々に大きな負担となった。彼女は、人々の腕から垂れ下がる焦げた皮膚と肉を描く「感情的に消耗する」作業について語った。
ある被爆者の証言を基に、彼女の絵画には水を飲む女性の姿が描かれた。
「最初は彼女の腕を胸に押し当てた姿を描いていましたが、やけどのため皮膚が接触するとひどく痛むはずなのです」と本田さんは述べた。
最近のデータによると、原爆の生存者は現在 10 万人未満、平均年齢は 86 歳だ。
基町高校卒業生の福本葵さん(19)は AFP に対して、「被爆者の話を直接聞くことができるのは、おそらく私たちの世代が最後だろう」と語った。
この危機感は、高砂さんを含む今年のプロジェクト参加者全員に浸透した。
「このプロジェクトに参加するまでは、広島出身であるにもかかわらず、原爆の被害は自分には遠いものと感じていた」と高砂さん。
しかし、広中さんの話を間接的に体験して、その考えは変わった。
「もはや傍観者ではいられない」と高砂さんは語った。
AFP