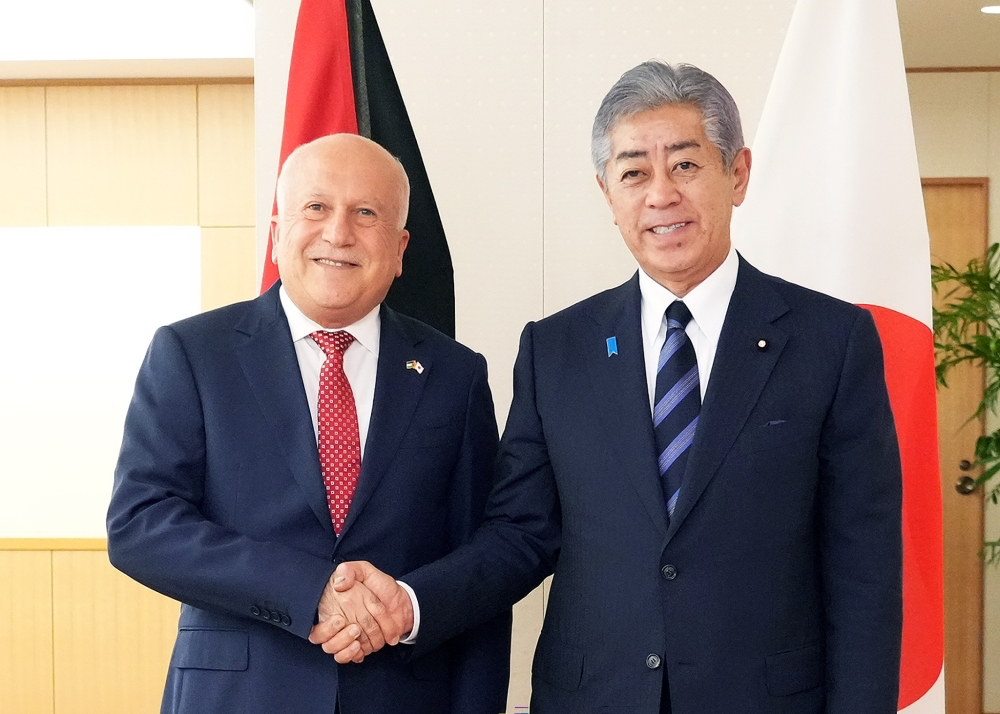- ARAB NEWS
- 01 Aug 2025
日本の卸売物価上昇率が急上昇、日銀の利上げ観測が強まる

東京:日本の1月の卸売物価上昇率は4.2%と7ヶ月ぶりの高水準に達し、5ヶ月連続で上昇率が加速した。
このデータは、日銀の植田和男総裁が水曜日に、食品コストの継続的な上昇は国民のインフレ期待に影響を与える可能性があると警告したことを受けて発表されたもので、中央銀行が物価上昇リスクを重視していることを強調している。
アナリストは、原材料費の上昇によるインフレ圧力は続くと見ているが、消費への打撃が日銀の早すぎる利上げを抑制する可能性があると警戒する向きもある。
農林中金総合研究所の南毅チーフエコノミストは「賃金は堅調に上昇しているが、食料品やエネルギーコストの上昇が消費者心理を圧迫し、家計支出の回復を遅らせている」と指摘する。「日銀が利上げペースを加速させる理由はほとんどない。
企業物価指数(CGPI)の上昇は、企業が商品やサービスに対して互いに請求する価格を測定するもので、市場予想の中央値4.0%を上回り、12月の改定値3.9%に続いた。
年間では2023年6月の4.5%上昇以来の高水準となった。農産物価格は36.2%上昇し、米、卵、肉の価格が着実に上昇したため、食料品コストは2.9%上昇した。
政府補助金の廃止がエネルギーコストを押し上げる一方、繊維、プラスチック、非鉄金属を含む幅広い価格上昇が見られた。
円ベースの輸入物価指数は、12月の1.4%上昇を修正した後、1月は前年同月比2.3%上昇した。
輸入コスト
水曜日に発表された米国のインフレ率の高いデータが、米国の利下げに対する市場の期待を後退させ、ドルが対円で1週間ぶりの高値に上昇したため、輸入物価はさらに上昇する可能性がある。
ドルは夜間に1.29%上昇し154.44円となり、木曜日のアジア市場では154.33円となった。日本の卸売物価統計が発表された後、ドル円はほとんど動かなかった。
日本国債(JGB)利回りはカーブ全体で上昇し、ベンチマークとなる10年物利回りは一時15年ぶりの高水準となる1.37%まで上昇したが、その後1.365%まで後退し、水曜日から2.5ベーシスポイント(bps)上昇した。
アナリストによると、米国債利回りの上昇とドナルド・トランプ米大統領の関税政策に対する不透明感が日本の利回り上昇の主な要因であり、市場はすでに7月の日銀利上げの可能性を80%程度織り込んでいるという。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のチーフ債券ストラジスト、六車直美氏は、「それでも、インフレ圧力が長引くため、日銀は今後数年間、あと数回の利上げに踏み切るだろう。
「日本はまだ、日銀が利上げによって需要を冷え込ませる段階にはないと思います」と六車氏は言う。「しかし、企業は原材料費や人件費の上昇を転嫁し続ける可能性が高く、日銀は少なくとも経済にとって中立的とみなされる水準まで金利を引き上げることになるでしょう」と付け加えた。
日銀は昨年、10年にわたる大規模な景気刺激策を終了し、1月に短期金利を0.5%まで引き上げた。これは、日本が日銀の2%のインフレ目標を持続的に達成する軌道に乗ったという見方によるものだ。
中央銀行は、幅広い賃上げが消費を下支えし、企業が商品だけでなくサービスも値上げし続けられるようになれば、さらに金利を引き上げる用意があることを示唆している。
日銀が目標とするのは卸売物価上昇率ではなく消費者物価上昇率だが、企業間取引価格の上昇は、家計が商品やサービスに支払う価格を遅れを伴って押し上げる可能性が高い。
日本の12月のコア消費者インフレ率は3.0%で、過去16ヶ月で最も速い年間ペースとなり、日銀の目標である2%を3年近く上回っている。
ロイター