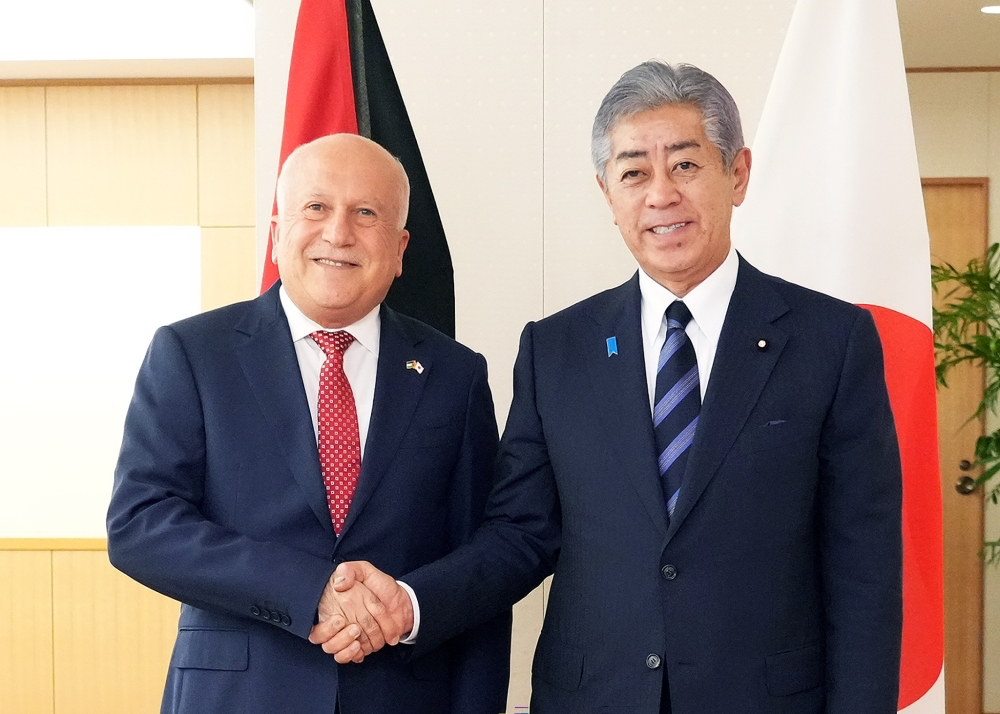- ARAB NEWS
- 01 Aug 2025
日銀、トランプ関税リスクにもかかわらず利上げ継続を明言

静岡:日銀の内田眞一副総裁は、金融市場やエコノミストの間で支配的な意見に沿ったペースで利上げを行うことができると述べ、借入コストが短期的に上昇する可能性があるとの期待を維持した。
内田副総裁は、日銀がいつ利上げに踏み切るかについては言及を避けたが、3月18-19日に開催される次回会合での追加利上げについては、「すべての会合で利上げを行うというわけではない」と述べ、基本的に否定した。
内田副総裁は19日の記者会見で、「(利上げに対する)経済や物価の反応を見てから、もう一度利上げするかどうかを決めればいい」と述べ、さらなる利上げに踏み切る前に、過去の政策措置の影響を見極めるのに時間をかけたい考えを示唆した。
「利上げのペースは、その時々の経済・物価情勢に左右される」と付け加えた。
日銀は、日本が2%のインフレ目標の持続的達成に向けて前進しているとの見方から、短期政策金利を1月の0.25%から0.5%に引き上げた。
内田副総裁は、ドナルド・トランプ米大統領の政策や地政学的緊張もあり、世界経済の先行きに強い不透明感があるため、警戒が必要だと警告した。
しかし、内田副総裁は日本経済に明るい見通しを示し、今年の企業と労働組合の賃金交渉で予想される堅調な賃上げが消費を下支えするだろう、と述べた。
基調的なインフレが徐々に加速し、賃金も上昇していることから、利上げは「長期的には経済活動と物価の安定につながるだろう」と述べた。
内田副総裁は記者会見に先立ち、静岡県内の企業経営者を前に行った講演で、「1月に発表した最新の経済・物価見通しが現実のものとなった場合、政策金利の引き上げを継続する」と述べた。
この発言は、トランプ大統領がカナダとメキシコからの製品に25%の関税をかけ、中国製品への関税を20%に倍増させ、他の国への課税の脅威が世界経済の減速懸念を煽っても、日銀の利上げの決意が今のところ揺らいでいないことを示唆している。
日銀のウェブサイトに掲載された内田副総裁の講演文に添付されたチャートによると、市場は7月頃に0.75%、そして来年早々に1%への利上げをおおよそ予測している。
ロイターが世論調査を行ったエコノミストの大半は、日銀が今年中にもう1回利上げを行うと予想しており、その可能性は第3四半期に最も高いと見ている。今月末の金利見直しの後、4月30日から5月1日にかけて理事会が開かれ、四半期ごとに新たな成長率とインフレ率の見通しが出される。
中立金利は目安にならない
内田副総裁は政策見通しについて強いヒントを出すことで知られている。追加利上げの時期について明確なシグナルがなかったため、市場は今回のコメントが中立的かややハト派的であるという印象を持った。
NLI総研のエコノミスト、上野剛氏は内田副総裁の発言について、「それほどタカ派的ではなかった。日銀の公式見解と一致している」と述べた。
内田氏は、日銀はコスト押し上げ圧力が弱まるにつれて、年間消費者インフレ率は目標である2%に向かって鈍化すると予想する一方、基調インフレ率は賃金上昇に伴って2%に向かって加速すると述べた。
「その結果、2025年度後半から2026年度にかけて、実際のインフレ率と基調的なインフレ率の両方が2%前後になると予想される」
そのころには、日銀の政策金利は経済にとって中立的な水準に近づいているだろう。日銀のスタッフは、インフレ率が2%前後で推移すると仮定した場合、名目ベースで1%から2.5%の範囲になると見積もっている、と内田氏は述べた。
しかし内田副総裁は、この試算は推定誤差の可能性があり、実際の金融政策に使うには幅が広すぎるとし、代わりに経済や物価の動向をよく見て利上げのタイミングを決めるよう求めた。
内田副総裁は、「実際には、(中立金利の水準は)経済や物価が利上げにどのように反応するかを調べればわかることだ」と述べた。
「予想通りのペースであれば、経済の反応を見ながら利上げを進めることも可能だろう」と語った。
日本の堅調な10-12月期GDPデータは、最近の強いインフレと相まって、近い将来の利上げ期待を強固にし、円と債券利回りを押し上げた。
堅調な企業・家計支出を背景に、昨年最終四半期の日本経済は年率2.8%拡大した。1月のコア消費者インフレ率は3.2%で、過去19ヶ月で最も速いペースとなり、日銀の2%目標をほぼ3年間上回っている。
ロイター