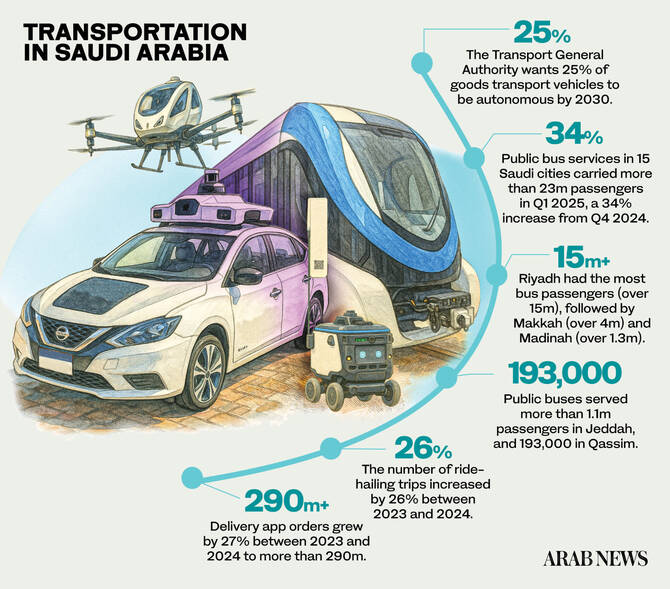- ARAB NEWS
- 16 Aug 2025
躍進するサウジアラビアの海水淡水化事業とその歴史

- 2021年にSWCC(サウジアラビア海水淡水化公社)は32基の生産プラントを運用して22億立方メートルの水を生産した。同社は水を蒸留する際の副産物として1時間あたり4,700万メガワットの電力も発電した
リナ・ガイヌリン、ハラ・ヒシャム・コウラ
リヤド: サウジアラビアの海水の淡水化は2010年の年間11億立方メートルから2021年には22億立方メートルへと過去10年間で倍増した。これは一部の既存プラントの大規模な改修と新技術の導入による成果だ。
例えば、リヤドやジュバイルに淡水を供給するサウジアラビア最大の海水淡水化プラントであるジュバイル2は年間生産能力を2014年の3億立方メートル未満から2021年には約3億8,000万立方メートルへと約30%増強している。
しかし、増大する国内の淡水需要に対応するためにサウジアラビアの海水淡水化産業はさらなるブレークスルーの検討に取り組もうとしている。
海水淡水化は、以下のサウジアラビアにおけるその歴史が示すように、同国経済にとって非常に重要な役割を担っている。
サウジアラビアにおける淡水化プロセスの歴史は1900年代初頭にまでさかのぼる。ジェッダの水需要増大に対応するために民間企業が蒸留コンデンサーを2基設置したのがサウジアラビアにおける初めての導入事例となった。
また、ヤンブーやジーザーンも同国の沿岸部の都市だが、同じアプローチをとり民間で独自に海水を蒸留するコンデンサーを開発したが、1965になると環境・水・農業省によって業界全体が国営化され管理されるようになった。
同国沿岸部でこの方式が普及し始めると1974年には同国の水蒸留事業を推進・監督するための独立行政法人「サウジアラビア海水淡水化公社」が設立された。
当初はコストもかかり効率性も高いとは言いがたいものだったが、人口が増加する王国のニーズには欠かせないものだった。
さらに、サウジでは地理的な条件から降雨などさまざまな種類の水資源へのアクセスも不利な状況にある。
そのため、選択肢は浅層または深層にある地下水と海水淡水化に限られていた。
2019年にジャーナル・オブ・ウォータープロセスエンジニアリングに掲載された調査報告によると、2007年にはわずか2,520万人だった人口が2018年には3,350万人に増加したことで飲料水の需要が70%増加した。
さらに、このペースで消費すると地下水は50年も持たないとも報告しており、政府が戦略的に検討・展開している海水の淡水化という選択肢を強調している。
2010年にSWCCは同国の東西両海岸にある30基の海水淡水化プラントで約11億立方メートルの淡水を生産し、同国の国内水需要の約50%を供給した。
2018年には同社はさらに生産能力を増強し、1日あたり520万立方メートル、1年間で19億立方メートルが供給可能となった。
そして2021年にはSWCC(サウジアラビア海水淡水化公社)は32基の生産プラントを運用して22億立方メートルの水を生産した。同社は水を蒸留する際の副産物として1時間あたり4,700万メガワットの電力も発電した。
主要都市では水の総消費量に占める淡水化水の割合がかなり高く、特にメッカ、ジェッダ、ターイフなどの都市では飲料水のほとんどが近隣の海水淡水化プラントから供給されている。
リヤドおよびサウジアラビアにおける2020年のシェアは63〜64%となった。
海水を飲料水にする手法としては、熱蒸留と逆浸透の2つが代表的だ。
前者は海水を熱して蒸発させ、塩分を水から分離し、気化したガスを凝縮・冷却して真水にする。
後者は海水を半透明の膜に通して塩分と水を分離するもので、無駄になるエネルギーが少ない。
さらにSWCCはビジョン2030の青写真の下で開発されている2つの再生可能エネルギープロジェクトに参画している。
サウジアラビアの海水淡水化の将来は、有望であると同時に難しさもある。そこでSWCCはもっと再生可能エネルギー源を海水淡水化プロジェクトに利用できるようにし、淡水化コストを削減することで淡水化効率の向上と二酸化炭素排出量の削減を同時に実現することを目指している。
現在の人口増加率が今後10〜15年間続くと仮定すると、2040年にサウジアラビアは最大で年間45億立方メートルの海水淡水化能力が必要になる可能性があると、2014年に発表された詳細な調査報告書が示唆している。実質的に2021年の生産量から再び倍増する必要がある。
海水淡水化手法の効率性や生産性がいかに高くなろうとも、現在の水の消費ペースでは、サウジアラビアは意識向上のキャンペーンや水の大量使用への課税など、需要減少を誘導せざるを得ないだろう。