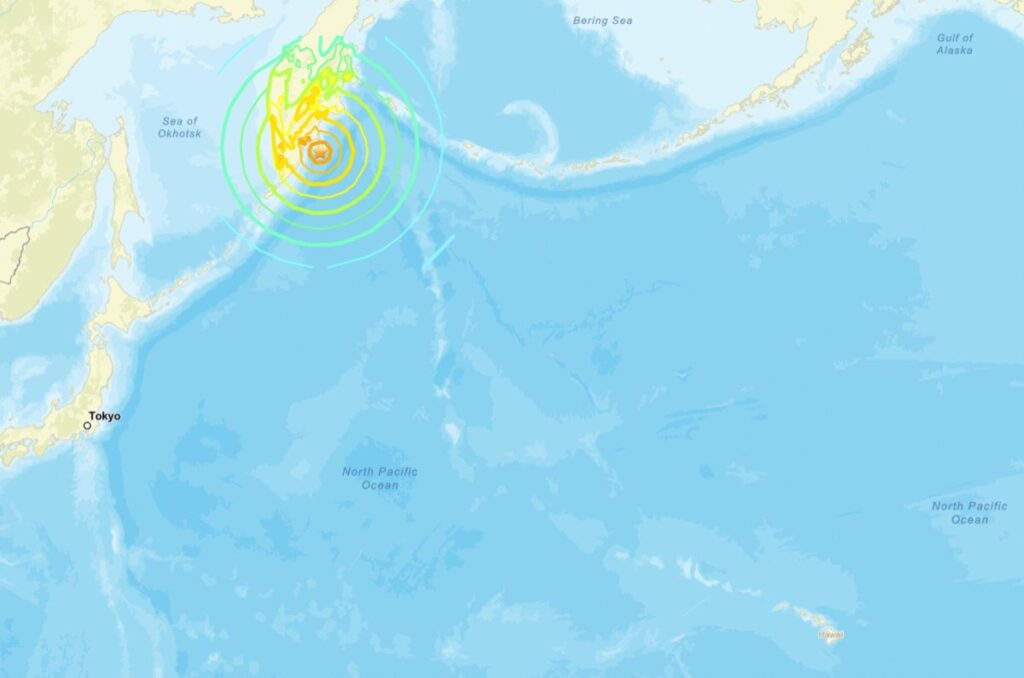- ARAB NEWS
- 31 Jul 2025
救命胴衣にGPS機能=同僚失った元職員発案―「一人でも多くの命を」―宮城・南三陸

一日たりとも仲間のことを考えない日はなかった。宮城県南三陸町の元総務課長高橋一清さん(63)は、東日本大震災の津波で多くの同僚を失った。「救命胴衣を着けていれば結果は変わっていたかもしれない」。高橋さんの提案をきっかけに、町内では津波や水害の被災者を早期に発見するため、全地球測位システム(GPS)機能を備えた救命胴衣を開発するプロジェクトが進んでいる。
地震直後は他の職員とともに、町の防災対策庁舎にいた。上司の指示で高台の避難所へ向かうと、さっきまでいた庁舎は津波にのまれ、町はがれきの海となっていた。
庁舎は骨組みだけが残り、町職員ら43人が犠牲となった。「自分も彼らと同じ運命だったはずだ」。震災後は被災者支援や町の復興事業に取り組み続けたが、気持ちが安らぐことのない日々を送っていた。
「救命胴衣を配備していれば、変わっていたかも」。ある日、防災事業に取り組む会社「ガーディアン72」を経営する知人の有馬朱美さんに胸の内を明かしたところ、GPSを内蔵した救命胴衣の開発計画につながった。
昨年10月には南三陸町の志津川湾で実証実験を実施。GPS付きの救命胴衣を着けたダイバーの位置を町役場内に設置した実験本部で特定し、連絡を受けた漁船が救助に向かうまでの流れを確認した。実験で大きな問題はなく、改良を重ねた上で今年5月の実用化を目指している。高橋さんは「一人でも多くの命を救うのに役立つといい」と期待を寄せる。
宮城県など日本でも津波犠牲者が出たチリ地震が起きた1960年に生まれ、周囲から「つなみっ子」と呼ばれて育ってきた。「『お前が生きているうちにまた来るからな』と言われるほど、この町で津波は人ごとではなかった」と話す。
現在は町の伝承館「南三陸311メモリアル」の顧問を務める。「また30年後に来るかもしれない。忘れていいはずがない」。これからも、地域のためにあの日の出来事を語り継ぐ。
時事通信