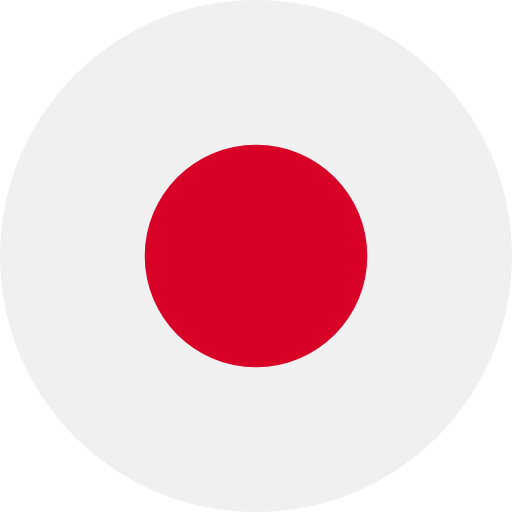- ARAB NEWS
- 20 Aug 2025
- Home
- 意見
- マジェド・アル・カタリ
- 長期的な成功のために取締役会がサステナビリティを主導しなければならない理由
長期的な成功のために取締役会がサステナビリティを主導しなければならない理由

環境、社会、ガバナンスへの配慮は、企業の周辺的な関心事から事業戦略の中心的な要素へと発展してきた。しかし、持続可能性へのコミットメントと取締役会レベルにおける説明責任の間には、ガバナンス上の大きなギャップが存在する。
サステナビリティを運営委員会に委任し続ける取締役会は、サステナビリティを効果的に監督する受託者責任を果たしていない。このような最高レベルでの説明責任のギャップは、コーポレート・ガバナンスの重要な課題として認識されつつある。
2023年のPwCの調査では、取締役の64%が気候変動を重大なビジネスリスクと認識しているにもかかわらず、自社の取締役会がESGに関する専門知識を有していると回答したのはわずか38%であった。このギャップは、気候変動に関する説明責任に対する投資家の要求が高まっているにもかかわらず存在している。
企業の持続可能性に関する誓約は野心的であることが多いが、必ずしも達成されていない。取締役会の監督もまだ不十分である。最近の調査によると、機関投資家の71%が、ほとんどの企業はESGの進捗状況を過大に評価しており、これは企業の持続可能性ガバナンスの信頼性の欠如を反映していると考えている。
2024年の調査では、S&P500企業のうち役員報酬をESG指標に連動させている企業はわずか23%で、ESGの専門知識を持つ取締役がいる企業はわずか17%であった。最高レベルにおける適切な説明責任がなければ、持続可能性の指標は単なるグリーンウォッシングになる危険性がある。
このような課題に対応するため、ESG課題に関する株主アクティビズムが急増しており、S&P500社における気候変動関連の議案は2020年以降88%増加している。また、EUの企業持続可能性報告指令やSECの気候変動開示規則により、企業報告義務が再構築されるなど、規制圧力も高まっている。
こうした圧力が高まる中、先進的な考えを持つ取締役会は、サステナビリティを中核的なガバナンス構造に組み込むことで対応している。高業績企業は、取締役会にサステナビリティ専門委員会を設置し、ESGリテラシーを資格として義務付け、気候変動への配慮を企業のリスク管理フレームワークに組み込んでいる傾向がある。
調査によると、ESGをしっかり実践している企業は財務面でも優れており、ESG上位企業の年間株主利益率は下位企業より10%高い。このパフォーマンス・プレミアムは、サステナビリティ・ガバナンスの役割がリスク軽減にとどまらず、戦略的機会の創出にまで及ぶことを強調している。
高業績企業は、サステナビリティ専門パネルを備えた取締役会を持ち、ESGリテラシーを資格として義務付け、気候変動への配慮を企業のリスク管理フレームワークに組み込んでいる。
マジェド・アルカタリ
このような視点の転換により、サステナビリティが単なる防衛手段ではなく、事業成長の推進力であることが明らかになった。
ユニリーバの取締役会レベルのサステナビリティ・リーダーシップは、コーポレート・レスポンシビリティ委員会に代表され、同社のサステナブル・リビング・プランを監督している。このガバナンス構造により、ユニリーバは一貫した株主利益を維持しながら、生産量当たりの炭素排出量を56%削減することに成功している。
同様に、デンマークのエネルギー企業であるオーステッドは、取締役会主導のグリーン転換により、二酸化炭素排出量を87%削減し、利益を毎年22%増加させている。
これらの事例を踏まえると、持続可能性を単なるコンプライアンスとして捉えるのではなく、イノベーションと競争優位性の原動力としなければならないことは明らかである。取締役会レベルで持続可能性を監督している企業は、そうでない企業に比べ、環境的利益をもたらす製品イノベーションを推進する可能性が約2.7倍高い。
2000年代初頭の会計不祥事後の規制枠組みが、取締役会に財務の専門知識を義務付けたように、規制機関は今こそESGの能力を求めるべきである。この転換は、取締役会が進化するビジネス環境に対応できるようにするために必要である。
財務資本が事業目標を達成するための主要な手段であることに変わりはないにもかかわらず、健全なサステナビリティ・ガバナンスを持たない企業は、よりサステナブルな同業他社に比べて最大30%高いコストに直面する可能性がある。これは、取締役会がもはや無視することのできない重大な財務的影響である。
結局のところ、サステナビリティ・ガバナンスは長期的な価値創造に不可欠なのである。2024年、ブラックロックのラリー・フィンクCEOは、気候変動リスクを投資リスクと位置づけた。
サステナビリティを主導できない取締役会は、環境と社会の変容によって急速に進化する環境の中で、株主価値を守り、向上させるという受託者としての義務を怠っている。
- マジェド・アルカタリ氏はサステナビリティのリーダーであり、環境、社会、ガバナンス、サステナビリティの目標達成に豊富な経験を持つエコロジー・エンジニアである。