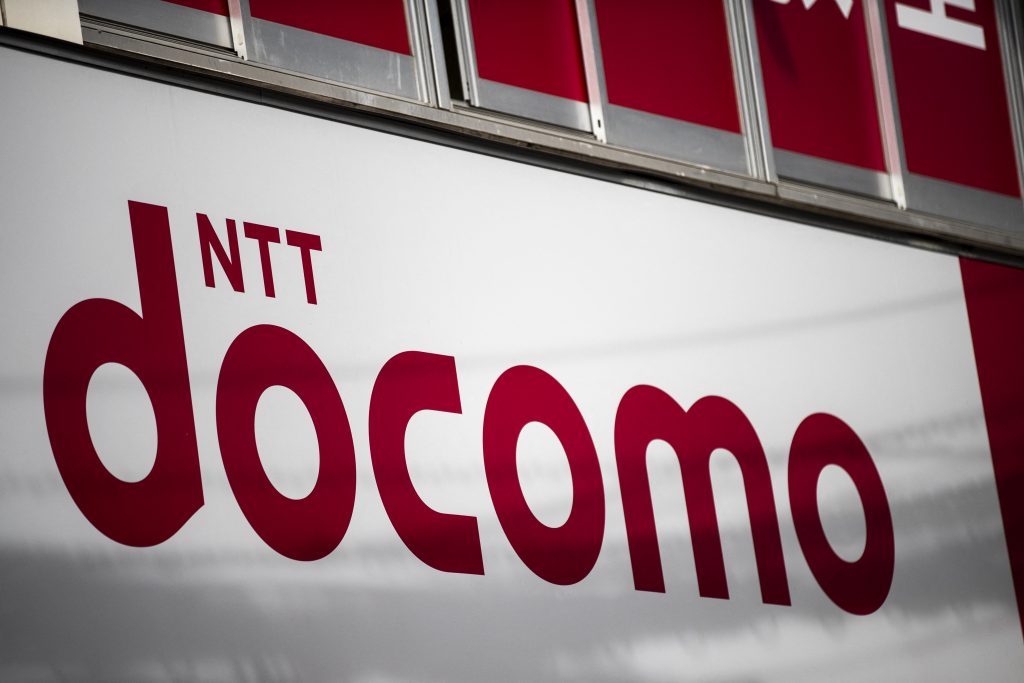- ARAB NEWS
- 15 Jun 2025
経済両立、成果残せず=コロナ対策、借金頼み継続―菅政権

昨年9月に発足した菅義偉政権は、新型コロナウイルス対策と経済活動の両立を目指してきた。安倍晋三前政権の経済政策「アベノミクス」を踏襲し、日銀の大規模な金融緩和で景気を下支えする一方、財政面は積極的な支出で借金頼みの構図が継続。コロナ後を見据え、デジタル化や脱炭素化も推進したが、経済回復の成果を残せないまま、退陣表明に追い込まれた。
2021年4~6月期の実質GDP(国内総生産)実額は年率換算で538兆円。コロナ前の19年10~12月期の546兆円に、いまだ届いていない。政府は年内の回復を見込むが、緊急事態宣言の影響で飲食や観光などの個人消費が低迷し、先行きは不透明だ。
菅政権は昨年末、景気のてこ入れに向け追加経済対策の経費19.2兆円を盛り込んだ20年度第3次補正予算を編成。一体的に編成した21年度予算は総額106.6兆円と9年連続で過去最大を更新した。
経済を優先して財政健全化を棚上げした結果、21年度予算の歳入に占める借金の割合を示す国債依存度は40.9%と7年ぶりの高水準。国債や借入金などの残高を合計した「国の借金」は今年6月末で1220.6兆円と、昨年9月末から約31兆円増加した。
巨額歳出を計上したものの、営業時間の短縮要請に応じた飲食店への協力金など支援の遅れも目立った。20年度から21年度への予算の繰越金は約30兆円に達し、迅速な支援に向けて課題を残した。「規模ありき」で策定された追加経済対策を受けた20年度3次補正では、脱炭素化の研究開発を支援する2兆円の基金創設などを計上。即効性に疑問符が付く事業が予算を膨らませた面もある。
一方、政府系金融機関などによる実質無利子・無担保融資といった企業の資金繰り支援を継続。日銀も政府の対策に呼応し、支援策を延長している。それでも、東京商工リサーチによると、コロナ関連倒産は今年8月末に累計2000件に達した。
菅政権は、携帯電話料金の引き下げなどで一定の成果を挙げた。ただ、デジタル化や脱炭素化など看板施策の多くが具体化されるのは、これからだ。規制改革も進める方針だったが、野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは「コロナ対策に忙殺され、構造改革を十分進めることができなかった」と指摘している。
時事通信