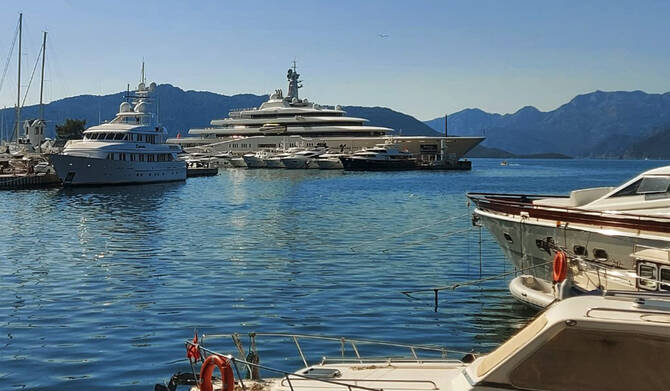- ARAB NEWS
- 16 Jun 2025
BRICSにおいて、トルコは戦略的影響力を拡大しようとしている

- 専門家は、この動きは経済的な動機によるものであり、アンカラの「戦略的自主性」への願望に沿うものであると指摘している
- 「トルコ政府は、欧米の揺るぎない覇権がこのまま継続することはあり得ないと考えている」
イスタンブール:トルコがBRICSに接近したのはNATO加盟国としては初めてのことかもしれないが、専門家は、この動きは経済的な動機によるものであり、アンカラの「戦略的自主性」への願望に沿うものであると指摘する。
レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の招待を受け、水曜日にロシアのカザン市で開催されるBRICSサミットに出席する。同大統領は、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの各国首脳と会談する予定である。
トルコは先月、新興市場国グループへの参加を要請したと発表した。参加が認められれば、西欧諸国に対抗する勢力として自らを位置づけるブロックにNATO加盟国が加わる初めてのケースとなる。
その加盟国のほとんどは、現在進行中の中東紛争をめぐって欧米と激しく対立しており、また、北京とモスクワの場合は、ウクライナ紛争に対する姿勢でも対立している。
BRICSは、その5つの創設メンバーの頭文字を取ったものであるが、今年、同盟国に中東から3カ国(ウクライナに対して使用する無人機をロシアに供給していると欧米が非難しているイランを含む)が加わった。
しかし専門家は、トルコの加盟申請は、欧米諸国やウクライナに背を向けることを意味するものではないと指摘している。ウクライナの外交トップは月曜日に訪問しており、NATOは言うまでもない。
「トルコ政府は、欧米諸国の同盟国ではない国々との関係を深め続けており、これはトルコが追求する戦略的自主性に沿ったものです」と、シンクタンク「カーネギー・ヨーロッパ」の研究員であるシナン・ウルゲン氏は述べた。
「しかし、このイニシアティブには経済的な側面もある。二国間の経済関係に良い影響を与えることが期待されている」と彼は述べた。
BRICS諸国は世界の人口の半分弱、世界総生産の約3分の1を占めている。
「プラットフォーム」として、EUのように加盟国に拘束力のある経済的義務を課すことはない。トルコは1999年からEU加盟交渉を続けている。
エルドアン大統領は先月、同様の指摘を行っている。「(BRICSに参加するなと言う人々は)トルコを何年もEUの門前で待たせているのと同じ人々だ」と彼は述べた。
「NATO加盟国だからといって、トルコがトルコ系・イスラム圏との関係を断つわけにはいかない。BRICSとASEANは、経済協力を発展させる機会を提供する枠組みなのだ」と彼は述べた。
ウルゲン氏は、この2つの問題は関連していると指摘した。
「トルコは、欧州との統合交渉、あるいは(1996年以降停滞している)関税同盟の強化さえ実現できていたならば、BRICSへの参加に向けたこのような動きは起こさなかっただろう」と述べた。
イスタンブール・カディルハス大学の国際関係論教授ソリ・オゼル氏は、トルコは世界の重心の変化に対応していると述べた。
「トルコ政府は、欧米の揺るぎない覇権がこのまま続くことはあり得ないことを認識している」と彼は言う。
「そして、多くの他の国々と同様に、非対称的な多極世界において新たな秩序が生まれた場合に、より大きな発言力を確保しようとしているのだ」
アンカラは、欧米の影響力、特に米国の影響力が「弱まっている」ことを利用し、より大きな行動の余地を生み出せるかどうかを見極めたいと考えている」、と彼は言う。
しかし、トルコは依然として「安全保障を重視する欧米の一部であり、その経済は間違いなく欧州経済の一部である」と付け加えた。
シンガポール在住のアナリスト、ゴークル・サーニー氏にとって、アンカラは「両方の世界から最良のものを手に入れたい」と考えている。
「トルコは欧米に隣接するメリットを享受したいと考えているが、欧米の一部になることは決してできないと理解しているため、非欧米のBRICS諸国と緊密に提携したいと考えている」と彼は述べた。
BRICSへの参加は「安全保障上の影響を伴わない」ため、ノーリスクの賭けであると彼は述べた。
「トルコは決してNATOを離脱することはない」とオゼル氏は述べたが、BRICSとの関係強化は「変化の必要性、新興の地域大国からより多くを得たいという願望」を反映している。
AFP