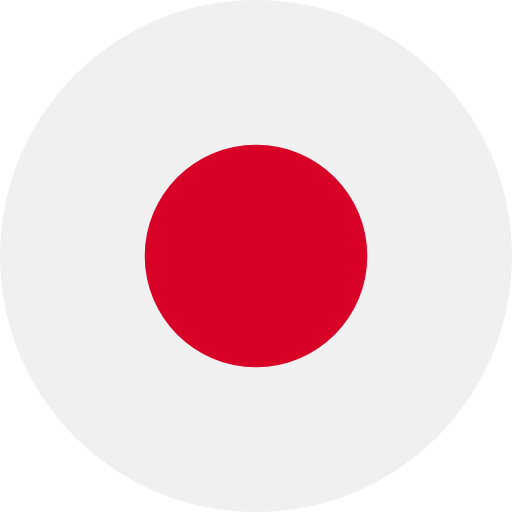- ARAB NEWS
- 17 Aug 2025
バグダッドの街角に今も刻まれるイラクの殺戮の時代

バグダッド:私にはバグダッドのそこここに、通りかかる度に黙祷を捧げる場所がある。死んでいった者たちのために。とある住宅街で。とあるレストランで。ミニバスの集まる広場で。
今、それらの場所では、人々は日々の仕事に忙しく、何年も前に今自分が歩いている場所で起こった惨劇を意識することはないのかもしれない。だが私にとっては、それら一つ一つの場所は、この目で見た殺戮、そこで苦しむ人々の痛みから切り離せるものではなくなっている。
私はAP通信のカメラマンとして、米国主導のイラク侵攻以来20年にわたる混乱期を取材した。侵攻後の宗派間の殺戮が続く中、私や他のカメラマンは、バグダッド周辺の自爆テロ、ロケット弾攻撃、銃撃戦の現場にほぼ毎日、時には1日に何度も駆けつけた。
イラクの人々は当時の恐怖を覚えているが、あまりにも多くの爆弾テロが発生したため、個々の攻撃の細かな記憶は薄れてしまっているかもしれない。このシリーズで私は、米国占領下の時期に撮影した写真と、現在の写真を組み合わせ、過去と現在を結びつけることを試みた。ここでは、そのうちのいくつかの背後にある物語を紹介する。

サドリヤ交差点
2007年4月18日、乗客を乗せたミニバスで混雑するこの大きな交差点で、自動車爆弾が群衆を吹き飛ばし、少なくとも140人が死亡した。この爆破事件は、単一の爆弾によるものとしては、米国の侵攻以来最も人的被害の大きなものの一つであった。
爆弾が爆発した時、私はその朝最初に起きた数十人の死者を出した別の爆破事件の現場にいた。そして、消防士たちが続いて起きたこの爆発現場に駆けつける際、私も同乗した。私たちは、サドリヤの現場にほぼ一番に到着した。焼けただれた肉の臭いが鼻腔に充満した。黒焦げの死体が、ねじれたミニバスの中に散らばっていた。生存者たちは、木製の野菜用カートに人間の破片を載せて運んでいた。
翌日、交差点に戻った時、私は少女を見たのだった――母親に連れられ、残された瓦礫やちぎれた遺体の中で何かを探していた。母親の足は裸足で、灰に覆われていた。彼女は顔に灰をこすりつけながら、行方不明の夫に向かって叫んでいた。「アフメド、どこに行ったの?アフメド、どこなの?娘たちにはあなたが必要なのよ」
少女の目には静かな恐怖が浮かんでいた。彼女は小さな妹を抱き、母親を追いかけながら、目の前の光景を受け止めていた。私は彼女を撮った。
数週間前、私は再びサドリヤにいた。ミニバスがクラクションを鳴らし、近くのストリートマーケットは人でごった返していた。16年前のあの日を追体験するのは、まるで映画を見るような感覚だった。爆弾の近くにいた人々が、跡形もなく蒸発してしまうように思えた。この交差点で、あの日彼らは最後のひとときを過ごしたのだ。

キャンプ・サラ地区
バグダッドのこの地区の名前は、かつて農地だったこの一帯を所有していた裕福なアルメニア系キリスト教徒の女性の名に由来している。20世紀初頭にトルコなどの弾圧から逃れたアルメニア人難民を、サラは自分の土地に受け入れ、1950年代にはほぼキリスト教徒だけの地区として整備された。
2006年10月4日、この地区の中心的な商店街通りで、わずか数十メートルの間隔で2つの自動車爆弾が数分以内に相次いで爆発した。大通りの1ブロック全体にわたり、建物は砕け、焼け焦げ、いくつかはほぼ完全に崩壊した。
爆発により少なくとも16人が死亡し、数十人が負傷した。何人かの若い男性が、虚弱な年配の女性を椅子に乗せて安全な場所に運ぶ光景も見られた。
また、防水シートでちぎれた遺体の一部を運ぶ人々もいた。危険から逃れるため、あるいは愛する人が生きているかどうかを確認するため、誰もが走り回っていた。
同地区に住むドゥレイドは、大きなショックを受け、爆破を背後で指示した過激派が聞いているかのように「おまえたちに神はいない」と叫んだ。「おまえたちはイスラム教徒ではない。(犠牲になった)この人たちはイラク人ではないのか?彼らが何をしたと言うんだ?」
この爆発は、何年にもわたってキリスト教徒地域を襲ったスンニ派イスラム過激派による多くの事件の一つに過ぎない。キャンプ・サラはかつてバグダッドで最も素晴らしいエリアのひとつで、おいしいレストランがあり、他の場所とは異なる雰囲気があった。現在、建物はきれいになったが、通りは電柱が動いていないところまで一見して以前と同様に見える。
しかし、実はすべてが変わってしまっているのだ。キャンプ・サラのキリスト教徒のほとんどは、暴力によってこの地を追われてしまった。デュレイドもバグダッドの別の場所に移り、私の写真で彼の隣に立っていた縞模様のシャツを着た男は米国にいる。キャンプ・サラはバグダッドの他の地域と同じようになり、その個性もまた、血塗られた時代の犠牲となってしまったのだ。

カラダ地区
2008年1月6日、イラク軍の創設を記念したアーミーデー。バグダッドの中流階級が住むカラダ地区の通りでは、ささやかなお祝いが行われていた。私は数人の報道カメラマンの一人としてそこにいた。住民たちが兵士たちに声援を送ろうと表に出てきていた。ある家のドアマン、アブ・アデルは、一人の兵士のライフルの銃口に花を挿し、頬にキスをした。次の瞬間、自爆テロの爆音が轟いた。
わずか数メートル離れたところにいた私は、地面に投げ出されて背中を強打したが、写真を撮り続けた。車や建物が焼け焦げ、引き裂かれた11人の死体があり、祝いのイベントは修羅場と化していた。犠牲者の中にはアブ・アデルもいた。
数週間前、私は再び同じ場所に行ってみた。そこは、別荘や住宅が建ち並ぶ静かな通りに戻っていた。写真を撮っていると、ある家のドアマンが声をかけてきた。名をアリ・アフメドといった。私は彼に、あの日ここにいたのかと尋ね、当時撮った爆発の時の写真を見せた。
アフメドは泣き出した。「あの日、私は死んでいたはずだった」と言う。アブ・アデルと一緒にアフメドも兵士のライフルに花を挿しに行こうとしていたが、その前に壊れた発電機を何とかしなければならなかったのだ。「ほんの数秒違えば死んでいた」とアフメド。彼と私は、写真の中で、血まみれの兵士たちの後ろに彼が写っているのを発見した。そして同じ場所で、彼を再び撮影した。年を取った彼が、若い当時の彼に重なっていった。
私もその日、あと少しで死ぬところだった。また他の時には、紙一重の生死の分かれ目の、あちら側にたまたま居てしまった人々を目にして、自分が死にどれだけ近づいていたのかを悟らされもした。私は、子供たちと妻のために神が私をここに残してくれたのだと自分に言い聞かせている。彼らと過ごす一日一日が、神からの贈り物なのだ。
例えば、夫婦が初めて恋に落ちた場所を再訪するときのように、特定の場所がある感情と分かちがたく結びついていることがある。
一部の場合、その感情とは恐怖に他ならないのである。