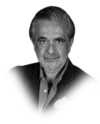- ARAB NEWS
- 15 Jun 2025
- Home
- 意見
- ラファエル・ヘルナンデス・デ・サンティアゴ
- AI時代の平和と共存を再考する
AI時代の平和と共存を再考する

新しい年の幕開けには、決意や約束がつきものである。より健康的な食事、より多くの運動、あるいは節約を目標に掲げても、2月ですでにピザをむさぼり食っている自分に気づくだけだ。
しかし、春が近づくにつれ、人類全体が遅ればせながら決意を新たにすることができるかもしれない: 共存を再考し、平和の新時代を目指すのだ。中東ほどこの呼びかけが急を要する地域はない。この地域は、しばしば笑い声よりも戦争の音が空に響く。
ピザにパイナップルは合うかをv議論している人もいれば、国境、宗教、数千年にわたる歴史について議論している人もいる。ユートピア的な理想ではなく、現実的な必然としてである。
哲学者たちは長い間、人間の対立という課題に取り組んできた。インマヌエル・カントは、そのエッセイ『恒久平和』の中で、永続的な平和は、個々の国家を超越した相互尊重と法的枠組みの基盤からしか生まれないと主張した。素晴らしいと思うだろう?しかし、何世紀も経った今、国際法は新年のスポーツジム入会よりも頻繁に無視されている。
皮肉はさておき、カントの考え方は依然として適切である。中東の紛争は、国際的なガバナンスと地域的な共感の両方の失敗を浮き彫りにしている。各国政府が守るつもりのない条約に署名する一方で、子どもたちは薄れゆく安全の記憶にしがみついている。ダライ・ラマは「自分自身と平和を築くまでは、外の世界で平和を得ることはできない」と語った。しかし、人類の内なる混乱は政策や行動に波及し、外的な混乱を生み出しているようだ。
それでもなお、哲学者たちは私たちに可能性を思い出させてくれる。マルティン・ブーバーの 「I-Thou 」関係の概念は、他者を目的のための手段ではなく、それ自体が目的であるとみなすことを強調している。この深遠な原則が地政学を導くとしたらどうだろう。各国がお互いをライバルや駒としてではなく、人間の物語を共有するパートナーとして扱う世界を想像してみてほしい。確かにこれはSF映画の筋書きのように聞こえるかもしれないが、産業、社会、イデオロギーを問わず、あらゆる革命は荒唐無稽なアイデアから始まったのだ。
人工知能を活用して、対立するグループ間の真の対話を促進するプラットフォームを作ることを想像してみてほしい。
ラファエル・エルナンデス・デ・サンティアゴ
テクノロジーは現代の諸刃の剣だ。声を増幅させ、心をつなぎ、革新を可能にする一方で、文字通りの意味でも比喩的な意味でも武器として使われてきた。しかし、このパラドックスの中にこそ、共存を再考するまたとない機会がある。
人工知能を活用して、対立するグループ間の真の対話を促進するプラットフォームを作ることを想像してみてほしい。AIが会話パターンや文化的ニュアンス、歴史的な不満を分析することで、溝を深めるのではなく、理解を促進することができるだろう。皮肉な楽観主義の精神で、AIが誤作動を起こし、かえって仮想戦争を引き起こさないことを祈ろう。
さらに、テクノロジーは透明性と説明責任のための新しいツールを提供することができる。ブロックチェーンは、暗号通貨や一攫千金詐欺と結び付けられることの多い流行語だが、平和のための強力な味方になりうる。スマート・コントラクトは、援助が意図した受取人に確実に届くようにし、分散型システムは人権侵害を隠蔽しにくくする可能性がある。
もちろん、どのような技術の進歩も、人間の変わろうとする意志に取って代わることはできない。アルベール・カミュが書いたように、「平和こそ、戦うに値する唯一の戦いである」。中東の問題は、そして実際、より広い世界の問題は、アイデンティティ、記憶、物語に深く根ざしている。共存を再考するには、謙虚さと勇気をもってこれらに立ち向かう必要がある。
絶望から希望が生まれるという皮肉を受け入れよう。ガザ、イエメン、そしてそれ以遠における紛争は、単なる危機ではなく、共存へのアプローチを再考する機会なのだ。スローガンや解決策にとどまらず、かつて壁があった場所に積極的に橋を架けることが求められているのだ。
哲学者の知恵、テクノロジーの可能性、そして人間の精神の強さを活用し、新たな物語を作り上げよう。
そして、万策尽きたら、せめてパイナップルはピザに乗せないという普遍的な真理だけは合意しよう。平和には時間がかかるかもしれないが、料理であれ何であれ、戦う価値のある戦いもあるのだ。
– ラファエル・エルナンデス・デ・サンティアゴ氏(子爵)はサウジアラビア在住のスペイン人で、ガルフ・リサーチ・センターで働いている。