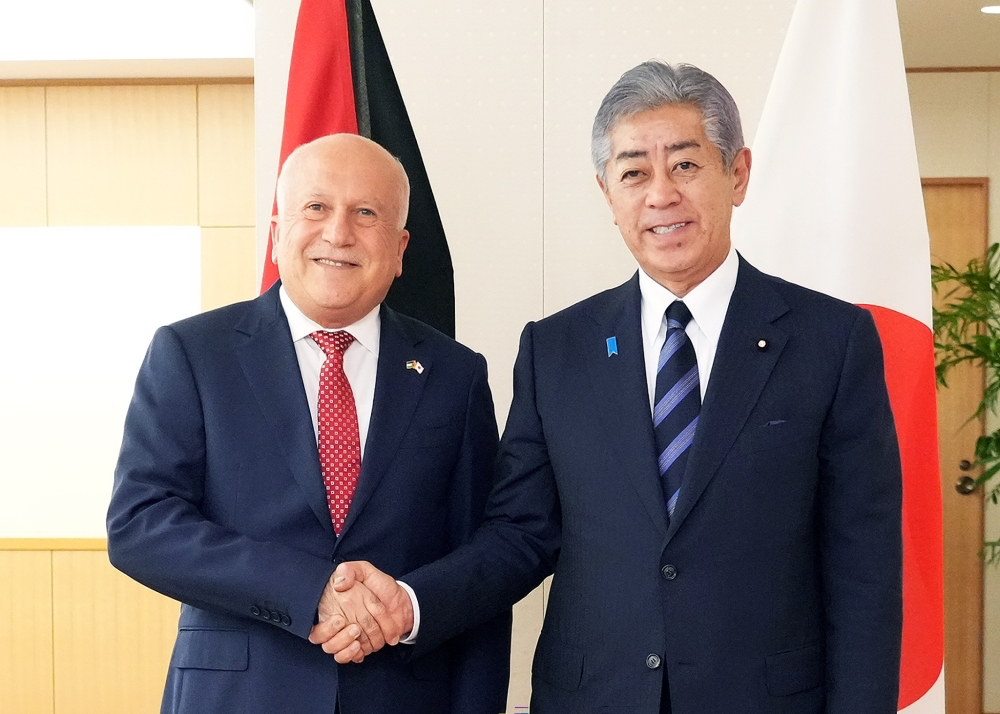- ARAB NEWS
- 01 Aug 2025
- Home
- 意見
- クリストファー・フィリップス
- 欧米は、より自己主張の強い中東に慣れる必要がある
欧米は、より自己主張の強い中東に慣れる必要がある

クリストファー・フィリップス
中東の同盟各国は、プーチン大統領のウクライナ侵攻に対する非難が極めて緩慢である。それどころか、どちらにも保険をかけているようだ。大半は、3月2日の、即時撤退を求める中途半端な国連総会決議を承認し、中には共同提案した者もいたが、同時に、欧米主導のロシア制裁に加わった国はなかった。最も強力なアメリカ同盟国の中には、さらに一歩踏み込み、欧米に反発している国もある。
イスラエルとトルコはともにモスクワとの緊密な関係を維持し、反ロシア同盟に加わるのではなく、自らを調停者として名乗りを上げた。サウジアラビアは、ロシアの石油供給減少による価格上昇を抑えるための増産を求めるワシントンの要請を拒否した。特にUAEは頑なである。リヤドと共に石油の増産を拒否し、さらに亡命中のロシアの「オリガルヒ」をドバイに迎え、モスクワの顧客であるシリアのバッシャール・アサド大統領を10年以上ぶりにアラブの首都に招き入れ、ワシントンを鼻であしらうような態度をとった。ある湾岸諸国のアナリストが指摘するように、これは西側諸国に対する明確なメッセージである。「これは我々の戦争ではない」ということだ。
西側諸国は不満を抱いているかもしれないが、中東の指導者たちのこうした主張は驚くにはあたらない。ウクライナ危機は、欧米とその同盟国の間に隠れた断層を露呈させたかもしれないが、その原因は根深く、消えることはないだろう。
第一の要因は、この10年間に世界のパワーが米国の支配から多極化へとシフトしていることである。中国の経済的台頭、ロシアの軍事的圧力、そして米国の影響力の相対的な低下により、ワシントンの権威は世界的に小さくなっている。米国が主導する対ロシア制裁体制に参加しないのは中東だけとは言い難い。アフリカ、南米、アジアのほぼすべての国が同様に消極的である。これは数十年前、西側のパワーは疑う余地がないと考えられていた時代とは大違いである。その時ワシントンは、同様の無謀な侵略を行ったサダム・フセインを孤立させ、制裁するよう世界を説得することができたのである。
ウクライナ危機は、欧米とその同盟国の間に隠れた断層を露呈させたかもしれないが、その原因は根深く、消えることはないだろう。
クリストファー・フィリップス
中東では、パワーバランスの変化に伴い、従来の西側同盟は米国以外の選択肢を持つようになった。UAE、サウジアラビア、イスラエル、トルコはいずれも中国、ロシアとの経済的、軍事的な関係を強化した。米国が主要なパートナーであり続けることに変わりはないが、他の選択肢の存在は、中東のプレイヤーに力を与え、米国からより大きな譲歩を引き出すための新たなレバレッジと、必要であればホワイトハウスに反抗する自信を与えているのである。
米国が中東から軍事的に撤退し、空白地帯が生まれる中で、このパワーシフトは、自己主張を強める地域諸国の政府によって埋められることになった。2003年にアメリカがイラクに介入して以来、アメリカは中東の紛争に関与することに消極的になり、代わりに他国にその余地を与えている。イランは地域紛争においてすでに大きな存在感を示し、ライバルであるサウジアラビアもテヘランに対抗するために同じような行動をとるようになった。さらにUAE、トルコ、カタールも加わり、これまで優勢だった米国が不在となったことで、直接または代理勢力を介して地域紛争への関与を強めている。
第二の要因は、中東諸国が、同盟国である欧米の政策に対して不満を募らせていることである。これらの政府は、それぞれが異なる優先順位を持っているが、いずれの場合も過去10年間の欧米の行動に対する不満のリストを容易に見つけることができる。トルコの場合は、シリア内戦、ダーイシュに対するクルド人グループの支援、2013年のエジプト軍によるムスリム同胞団政権打倒に対する黙認。イスラエルの場合は、2015年のイランとの核取引に最初に合意し、その後今日まで再交渉を続けてきたことに不満を持っている。サウジアラビアとUAEにとっては、イラン核合意やイエメンでの取り組みへの支援が少なすぎることなどが不満だ。
不満のリストは続く。その結果、それぞれの国が、欧米政府をかつてよりはるかに信頼していない。どの国も安全保障と経済の重要な同盟国である米国との関係を断ち切ろうとしているわけではない。しかし、かつて存在した敬意はとうに失われている。
中東諸国の政府は、同盟関係において、より取引重視のスタンスになりつつある。そして、自国の利益を欧米の同盟国の利益に従属させることに、ますます消極的になっている。このような状況は長い間続いており、欧米諸国は驚くべきではない。ワシントンをはじめとする西側諸国は、リヤド、アブダビ、テルアビブ、アンカラが世界的危機の際に自分たちの背後に控えていると期待していたのかもしれない。しかしウクライナ戦争は、そうした同盟国を当然視することへの危険性を露呈させたのである。時代は変わり、ウクライナ戦争の結果がどうであれ、中東の独立性と自己主張の強さは今後も続くと思われる。
・クリストファー・フィリップスはロンドン大学クイーン・メアリー校の国際関係学教授であり、『シリアをめぐる新たな国際対立(原題:The Battle for Syria : International Rivalry in the New Middle East)』の著者、『What next for Britain in the Middle East?』の共編著者である。ツイッター: @cjophillips