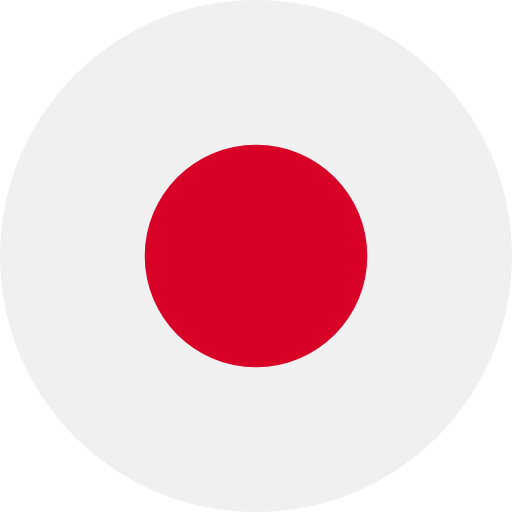- ARAB NEWS
- 15 Jun 2025
- Home
- 意見
- ジョン・C・フルスマン博士
- スキャンダルがバイデン政権の新たな危機となる
スキャンダルがバイデン政権の新たな危機となる

偉大なるナポレオンは、素晴らしい名言を残した。「死は何でもない。だが、敗北と不名誉を生きることは、毎日死ぬことに等しい」。この明快な判断基準によれば、混乱をさまようジョー・バイデン大統領政権は日々死んでいることになる。
野心的な国内政策の実現の失敗、ウクライナ戦争についての危険な失言、準備のない国民をインフレの餌食にしたこと、問題の核心がどこにあるにせよ、ホワイトハウスは明らかに政策的に守勢に立たされており、その事実は大統領の職務能力支持率に如実に反映されている。
バイデン大統領は、視聴者の不信感を買いつつ、ホワイトハウスの弁護役を務める米国の主流メディアのますます必死な努力によって守られているにもかかわらず、国民はまったく騙されていない。Real Clear Politicsの世論調査の平均では、大統領支持率は41%と低く、54%が大統領の仕事を支持しないと答えた。
このコラムで明らかにしてきたように、米国の世論調査を読むときは、大統領選の患者の体温だと考えるのが一番いい。ワシントンの住人たちは、最も下っ端の郵便物に対応する立法担当職員から国務長官まで、誰もが他の国民が野球のスコアを読むのと同じように世論調査に向かう。熱心に、貪欲に、絶え間なく。
ホワイトハウスの内部関係者の経験則としては、大統領の支持率が60%を超える場合は、国内での人気の高さによって議会の決定に対しかなりの影響力を持つという。1936年のフランクリン・ルーズベルト大統領、1952年のドワイト・D・アイゼンハワー大統領、1964年のリンドン・ジョンソン大統領、1984年のロナルド・レーガン大統領などが良い例だ。だが、支持率が40%以下に落ちると、大統領の立場はあまりにも弱くなり、ホワイトハウスは大統領が死亡したという噂を消すために時間を費やす羽目になる。バイデン大統領の支持率はこの危険な数値よりほんのわずか上回るだけであり、存在感を示し続けるのに苦労している。
バイデン大統領にとってさらに悪いことに、ずらりと並んだ国内の課題、ウクライナについての失言、横行するインフレの上昇に加え、ホワイトハウスは新たな危機的状況に見舞われている。長いことふれられていなかったバイデン大統領の息子、ハンター氏に関するスキャンダルだ。ハンター・バイデン氏の武勇伝は、2020年の選挙戦中に主流メディアが何とか葬り去っていたが、この能天気な大統領の息子が不透明な税務処理と国際ビジネス取引についてデラウェア州の連邦検事局に調査されているというニュースをきっかけに、再びその醜態をさらすこととなった。
ホワイトハウスは明らかに政策的に守勢に立たされており、その事実は大統領の職務能力支持率に如実に反映されている。
ジョン・C・ハルスマン博士
贔屓目に見ても、ハンター・バイデン氏は、有名な父親を持つことを利用して見合わないキャリアを積んできたといえる。たとえば、エネルギー分野でインターンを務めるほどの資格すらないにもかかわらず、ウクライナのエネルギー企業の役員に就任し、一見、何もしていないのに数百万ドルを稼いでいる。この会社は、ハンター氏の父親の地位を利用しようとしたと考えるのが妥当だろう。そうでなければ、ハンター氏を雇う論理的な理由は何一つないように思われる。さらに悪いことに、ハンター氏はアメリカの戦略的競争相手として台頭しつつある中国でも不透明な仕事に関わっていた。ビジネス取引を行うために、当時、副大統領を務めていた父親の訪問に便乗して同行してすらいたのだ。
大陪審が召集され、これらすべてを調査することになっている。さらに、脱税の可能性も高い。だが、問題はハンター・バイデン氏だけにとどまらない。大陪審の作業からリークされた情報が、イギリスの新聞「タイムズ」などの信用のあるメディアに掲載された。これは、ハンター氏の元ビジネスパートナー、トニー・ボブリンスキー氏が繰り返し語ってきたことを裏付けている。ジョー・バイデン大統領は、ハンター氏の不正な取引に深く関わっていたというのだ。特に不都合な証拠となるのはボブリンスキー氏が公開したメールにある「The Big GuyのためにHが10を確保(10 held by H for the Big Guy)」という一節で、これは現在は存在しない中国のエネルギー企業との事業における出資比率を指しているという。「H」はおそらくハンター氏を指している可能性、また、「The Big Guy」が誰であるかは、超能力者でなくても容易に推測できる。この明らかな仮定は、自発的にFBIに協力しているボブリンスキー氏によって確認されている。
だが、大統領にとってはるかに悪いのは、選挙期間中、ほとんど信じられないような発言をいくつもしていることだ。当時(驚くべきことに)、怪しいほどに無関心だった米国の主流メディアはこれらの発言をフォローアップしなかった。息子のビジネスについて何か知っていることはあるかという質問に対し、バイデン候補は息子のビジネスについては話すらしたことがないと答えた。それを見ながらテレビに向かって叫んだのを覚えている。「一度も?クリスマスは?感謝祭は?子どもたちが集まる時には?息子にビジネスの調子はどうかとか、遠く離れた場所で何をしているのかまったく聞いたことがないだって?」。これは、ありがちな誤解を招く発言に対する私個人の反射的で理屈的な反応かもしれない。だが、先ほど述べたように、信じられないことだが、バイデン氏がこの発言についてつっこまれることはなかった。つまり、現在までは、ということだが。
大陪審の現実と山のような不適切な事実により、アメリカの二大左翼紙「ワシントン・ポスト」と「ニューヨーク・タイムズ」も、渋々ながらもようやく、ハンター・バイデン氏の話を根も葉もない悪評とするのではなく、追跡調査が必要だと認めざるを得なくなった。「ニューヨーク・ポスト」が最初に疑惑を報じてから1年以上経ってのことだ。当時のバイデン氏の政治チームにとっては好都合なことに、2020年の選挙結果に影響を与えたかもしれないスキャンダルは葬り去られた。だが、今や不都合なことに、同じスキャンダルは吸血鬼のように墓場から蘇ってきた。米国の主流メディアの八百長めいた最善の努力にもかかわらずだ。この話題は今後何年にもわたって、すでに窮地に立っているバイデン大統領政権を苦しめ続けるに違いない。
- ジョン・C・ハルスマン氏は、世界の主要な政治リスクコンサルティング会社の一つ、ジョン・C・ハルスマンエンタープライズの社長兼マネージングパートナー。また、ロンドン・シティの新聞「シティAM」のシニア・コラムニストでもある。連絡は、johnhulsman.substack.comまで。